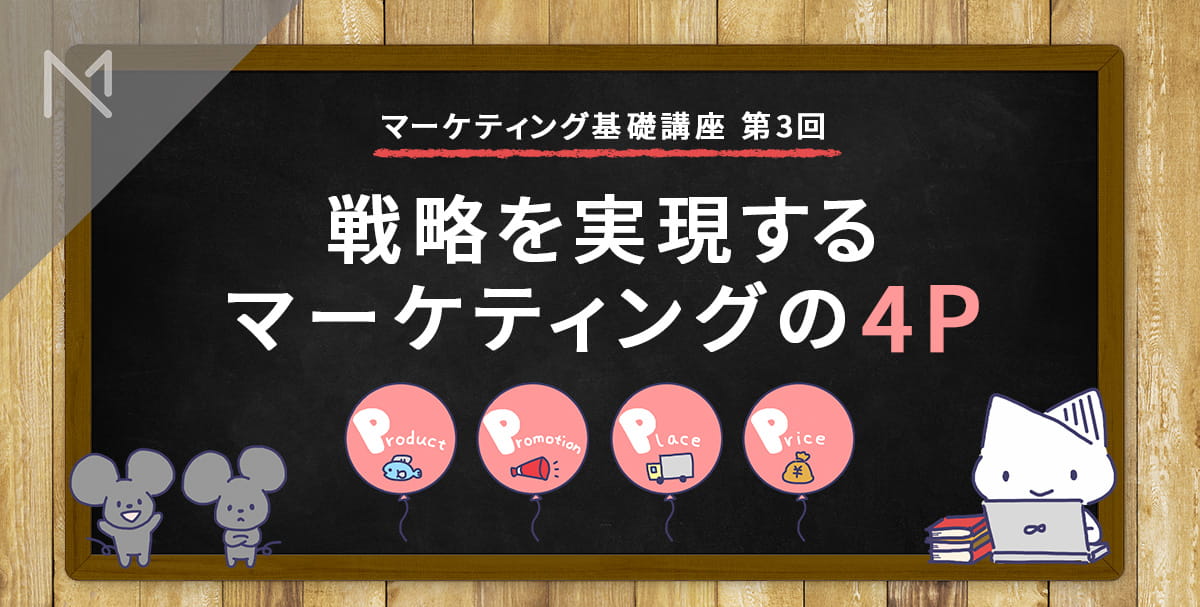O2Oとは「Online to Offline」の略で、日本語にすると「オンラインからオフラインへ」と訳されるマーケティング用語のひとつです。オンライン上の施策をきっかけに、オフラインの実店舗へ足を運んでもらうための施策を意味します。
O2Oに類似する言葉にはオムニチャネルやOMOがあり、近年注目を集めています。それぞれどう異なり、具体的にはどのような施策があるのでしょうか。
この記事では、O2Oの基本をあらためておさらいしつつ、オムニチャネルやOMOとの違いについても解説します。
目次
O2Oの押さえておきたい基本
O2O(オンラインからオフラインへ)は「OtoO」や「On2Off」と表記されることもあります。O2Oはどのような背景で浸透したのでしょうか。
O2Oとは?
O2O(読み方:オーツーオー)とは、わかりやすく言うとインターネットから得た情報に興味をもった消費者を、店舗などのオフラインへと誘導する施策のことです。オンラインでの接触がオフラインでの購買行動に影響を及ぼすような施策をO2Oと言うこともあります。
O2Oが注目を集めるようになったのは、2010年前後のことです。もともとO2Oは、「ショールーミング」対策でもあったと言われています。ショールーミングとは、実店舗では商品を見るだけで、より低価格で購入すべくオンラインで検索する消費行動を意味します。商品の素材や質感を確認するために店舗へ足を運ぶものの、実際の購入は実店舗よりも安く販売されるECサイトを利用するということです。スマートフォンの普及に伴い、いつ・どこでもインターネットにアクセスして情報が得られるようになったことや、価格比較サイトの登場などが、ショールーミングに拍車をかけたとされています。また、SNSの普及により、口コミを検索しやすくなったことも影響しているでしょう。
このようにオンラインへと消費者が流れていく一方で、接客や試供など実店舗でなければ実現できないサービスがあるのも事実です。例えば、次のような事柄は店舗でなければ体験するのは難しいでしょう。
- 気になるワンピースの色や着心地を試着で確かめる
- 雑貨屋で、友人への贈り物について、店員さんにおすすめのアイテムを聞く
- ゴルフクラブを試しに打って、重さや感触を確かめる
など
O2Oが注目を集めている背景には、オフラインによる顧客体験の価値が再評価されるようになったことが挙げられます。実際に商品を目にしたり、手に触れたりしてこそ、満足感が得られるケースも存在するのです。O2Oは、利便性が高く効率の良いオンラインと、直接的に顧客体験を提供できるオフラインを組み合わせ、購買へとつなげる施策と言えるでしょう。

O2Oの主な目的
O2Oの目的は、主に2つあります。新規顧客の獲得と再来店の促進です。
O2Oではインターネットの利用により、実店舗のことを知らない層や商品に興味を持つ可能性が高い潜在顧客にもアプローチすることが可能です。そのため、O2O施策の導入は新規顧客の獲得に有効と言われています。
また、O2Oはプッシュ通知やクーポンの発行などにより、店舗への再来店を促すこともできます。再来店率の向上やリピーターの獲得を目指すには、実店舗でのみ使用可能なクーポンや特典の配布などが効果的です。既存顧客に対し、実店舗へ足を運んでもらうメリットをつくることがポイントです。
O2Oの特徴とメリット
O2OはメールマガジンやSNSなどで顧客にアプローチし、即効性のある施策を打つことができます。例えば、利用期限を設けて実店舗で使えるクーポンを配布すると、その期間中に店舗へ訪れる顧客が増え、売り上げの増加につながる可能性があります。雨の日にお客様が少ないと感じたら、その場で雨の日限定のクーポンを配信し、来店を促進することもできるのです。
また、オンラインの特徴を活かして明確な数字(売上や来店者数など)がデータとして記録されることも、O2Oのメリットのひとつです。O2Oはマーケティング施策の効果を測定しやすく、オンライン上で行った施策の数値を計測できるのはもちろん、オフラインへどれだけ誘導したか測定することも可能です。例えばクーポンを発行した場合、実店舗で使用された件数を調べれば、施策の効果を分析できるでしょう。
O2Oの具体的な事例
O2Oへの理解をより深められるよう、ここでは具体例をご紹介します。コストを抑えた施策を打てる点もO2Oのメリットです。
ECサイトと実店舗の連携
ECサイトと実店舗の連携は多くの企業で見られるようになっているのではないでしょうか。具体的な連携の仕方としては、ECサイトで購入した商品を店舗で受け取れるサービスの提供や、ECサイトと店舗の両方で貯まるポイントシステムの運用などが挙げられます。また、近年の消費行動には、Webサイトで商品の情報を検索し、実店舗で購入する「ウェブルーミング」もあり、ECサイト上で店舗の在庫を確認できるようにしている企業も見られます。
・事例
現場作業・工場作業向けのワーキングウエアを開発する「ワークマン」では、ワークマンオンラインストアの会員限定で、注文した商品を近くの実店舗で受け取ることができるサービスを提供しています。オンラインストアなら24時間いつでも対応しているため、顧客は商品が必要になったときや都合の良いタイミングでの注文が可能です。
また、ネットで注文した商品は全国にあるワークマンショップの店頭にて、1点からでも送料無料で受け取れ、店舗で試着してから購入できます。店舗での受け取り期間は「店舗到着メール送信日から10日以内」とされているものの、希望する店舗に在庫がある場合は、注文から最短3時間での店舗受け取りが可能です。
ワークマンオンラインストアを利用する顧客の約7割がお得感や利便性から店舗受け取りを選択しており、ワークマンは将来的にはオンラインストアの注文商品すべてを店舗で受け取る形式へ変更することを検討しています。
クーポンの配布
クーポンの配布は、「店舗限定」や「期間限定」などとすることにより、来店を促し、売上アップにつなげるのが目的です。メールマガジン会員限定のクーポンや、公式SNSで発行するクーポンなどの例があります。また、クーポンを活用し、既存顧客から新規顧客の獲得につなげる工夫も効果的でしょう。顧客が知人や友人を紹介することによって両者に発行されるクーポンなどがその例です。

SNSの活用
TwitterやInstagramなどのSNSを活用した情報発信も効果的です。例えば新商品やセールの情報を配信するのはもちろん、特定の投稿をシェアした顧客に特典を与える方法もあります。Twitterでフォロー&リツイートによりクーポンや商品のプレゼントを行うキャンペーンツイートを見たことがある方もいるのではないでしょうか。SNSは自社の集客・販促ツールとして活用でき、投稿がうまく拡散されれば費用を抑えてより多くの見込み客へのアプローチが可能です。
・事例
化粧品メーカーの「ポーラ」では、Twitterのインスタントウィンキャンペーン(※1)を活用し、オンラインからリアル店舗につなげる施策を実施しました。ポーラによるO2O施策の目的は、デジタル面での知名度を上げることと、店舗への来店ハードルを下げてリアルまでつなげることです。参加のハードルが低く、拡散によるリーチの獲得が期待できたことからインスタントウィンキャンペーンを利用しました。
施策を行った結果、公式アカウントのフォロワー数は5日間で約7,000人増え、Twitter経由のブランドサイトへの流入数はキャンペーン前後で2倍に増加しました。定性的な部分では、SNS上での盛り上がりが可視化されたことで、店舗で働くパートナーの方々の士気が上がったと言います。
また、コンビニエンスストアの「ローソン」では、Twitterの公式アカウントをフォローしたうえで特定のハッシュタグ付きで投稿すると、抽選で商品の無料券や値引き券が当たる施策を定期的に実施しています。特にローソンで人気の高いスイーツ商品をフックにしたキャンペーンを行い、フォロワー数を大きく伸ばすことに成功しました。
さらに、キャンペーンや新商品に関する情報がPV数の多いニュースメディアに取り上げられると、公式アカウントがリツイートして話題化させていると言います。
(※1)応募するとその場ですぐに抽選結果がわかる懸賞のこと。Twitterでは応募の条件として、アカウントのフォローや投稿のリツイート、ハッシュタグを付けたツイートを求めることが多い。
関連記事:
化粧品メーカーのポーラが、たった5日間でフォロワーを7000人獲得したTwitter運用施策のポイントとは?
Twitterフォロワー数で企業の公式アカウントNo.1、ローソン白井明子が語る フォロワー数の伸ばし方と情報の届け方、視野を広げる勉強法
位置情報との連動
スマホに搭載されたGPS(位置情報)と連動させ、来店を促す方法もあります。一般的な活用例は、顧客の来店時や店舗付近を通った際に、クーポンやポイントを付与するものです。付与するクーポンやポイントに利用期限を設ければ、利用の促進につなげることもできます。
QRコードの活用
QRコードのわかりやすい活用例が「LINEアカウントへの友だち登録」です。初回購入後のレシートやレジの横、店内のPOPなどにQRコードを掲載し、友だち登録を促します。登録してもらったユーザーにはクーポンやセール情報を発信し、再来店へとつなげるのです。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
O2Oとオムニチャネル、OMOの違い
O2Oと同じく知られる用語にOMOとオムニチャネルがあります。それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
オムニチャネル
オムニチャネルとは、実店舗やECサイト、公式アプリなど、オフラインとオンラインの境目なく顧客とのつながりを関連付けることです。複数のチャネルでアプローチすることにより、顧客はオンラインかオフラインかを意識せず、どのチャネルからも同様の購入体験が得られるようになります。例えば、次のようなイメージです。
- ECサイトで商品を検索し、在庫を確認
- 店舗に来店し、チェックイン機能でポイントを入手
- 店舗で商品を購入
- 商品購入時にスマートフォンアプリのクーポン、ポイントを使用
オムニチャネルは、顧客満足度の向上によってリピーターの増加が見込めるため、既存顧客の囲い込みを目的に実施されることが多い取り組みです。
・事例
リアル書店・本の通販・電子書籍が連動したハイブリッド型総合書店の「honto」では、店頭の在庫検索や店舗での商品の取り置き依頼、ポイントカード機能、購入した書籍のリスト管理などを行える専用アプリ「honto with」を提供しています。店舗の在庫検索を起点に、顧客が異なるチャネル(店舗・通販・電子書籍)を横断してスムーズな購入体験を得られるよう、サポートするためのアプリです。
紙の本や電子書籍の購入、「honto with」のチェックイン機能などで貯めたポイントは「1ポイント=1円相当」として、hontoポイントサービス実施店やオンラインストアでの購入時に利用可能です。ポイントには有効期限があることから、顧客に商品の購入を促すような仕組みになっています。
OMO
OMOは「Online Merges with Offline」の略で「オンラインとオフラインの融合」と訳されます。オンラインとオフラインの境目をなくしてどちらでも同様のサービスを受けられるようにし、顧客体験の向上を目指す考え方です。OMOはO2Oとオムニチャネルを発展させた考え方とも言えます。
例えば、中国の有名なスーパーマーケット・盒馬鮮生(フーマーションシェン)では、商品棚のバーコードをアプリでスキャンすると商品の特徴やおすすめレシピを確認できるなど、オンラインとオフラインの垣根のないシームレスな買い物体験を提供しています。
3つのマーケティング用語をあらためてまとめると、次の通りです。
- O2O:オンラインからオフラインへと顧客を誘導する施策
- オムニチャネル:顧客と接点を持つチャネルを連携させ、アプローチする方法
- OMO:オンラインとオフラインのチャネルの区別なくサービスを提供する考え方
O2Oで店舗にしか実現できない価値の提供を
O2Oとはオンラインからオフラインへと誘導するための施策のことで、主な目的は「新規顧客の獲得」と「再来店の促進」です。コストを抑えて実施でき、即効性が高く、効果測定しやすいというメリットがあります。
効果的なO2O施策はさまざまあり、ECサイトと実店舗の連携やクーポンの配布、 SNSの活用などが挙げられます。実際に企業が行っているO2Oの事例や、オムニチャネル、OMOとの違いも含めて、この記事がマーケティング戦略の参考になれば幸いです。
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン