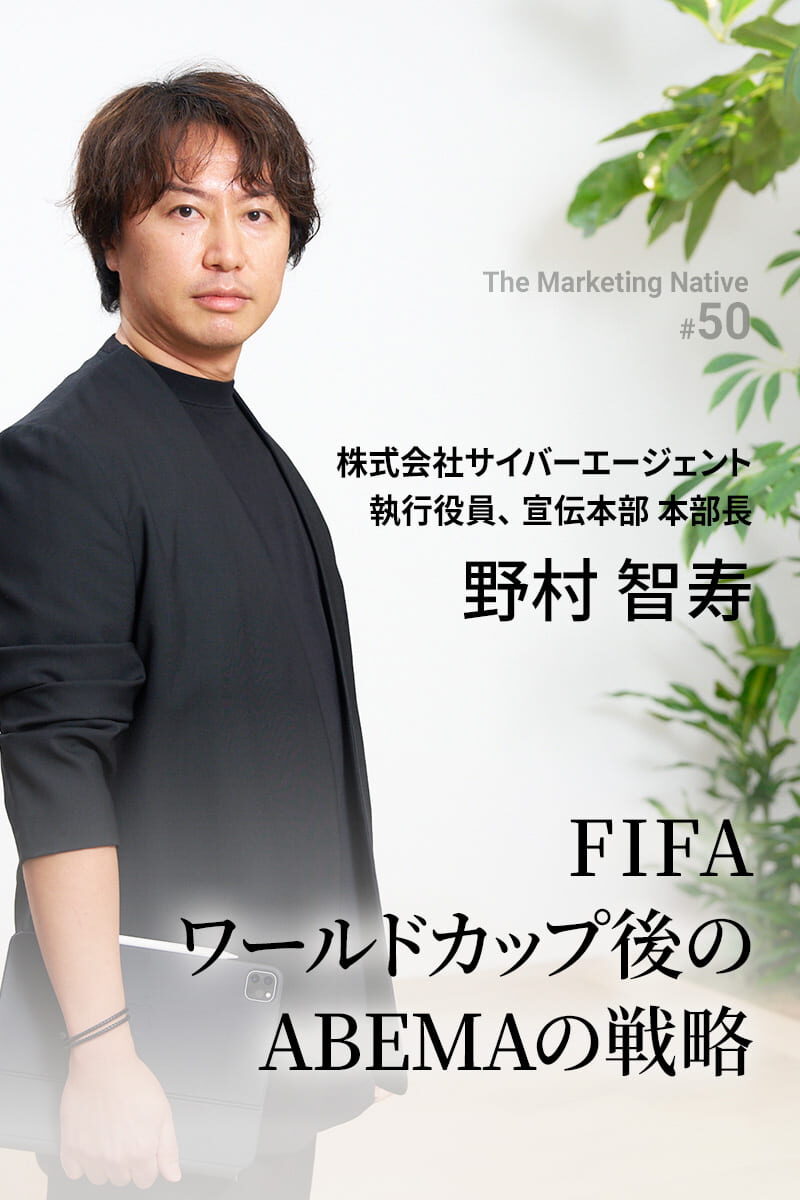多くの日本人を興奮させた「FIFA ワールドカップ カタール 2022」。年が明けても熱気は冷めることがなく、三笘薫選手ら欧州リーグ所属選手の活躍をはじめ、30周年を迎えたJリーグの盛り上がりもあり、余韻が続いています。
FIFA ワールドカップの熱狂に大きく貢献した1つが「ABEMA」でしょう。全64試合を無料で生中継し、「ABEMA FIFA ワールドカップ 2022 プロジェクト」のゼネラルマネージャー(GM)を務めた本田圭佑さんによる解説も大きな反響を呼びました。
ABEMAとしては、ワールドカップで新たに獲得した視聴者をつなぎ止め、そのまま事業成長へと結びつけたいはず。そのためにどんな戦略を考えているのでしょうか。
今回はサイバーエージェント執行役員、宣伝本部 本部長でABEMA「FIFA ワールドカップ カタール 2022」統括責任者を務めた野村智寿さんに話を聞きました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:永山 昌克)
目次
ワールドカップについて今だから感じること
――昨年のことになりますが、あらためて「FIFA ワールドカップ カタール 2022」全64試合無料生中継の成功、おめでとうございます。今振り返って良かったこと、課題などありましたら教えてください。
ありがとうございます。成功かどうかは皆さまにご評価いただくことだと思いますが、ABEMAとしてはテレビ朝日の皆さまとの強力なタッグのもと、無事に全64試合の無料生中継を終えることができ、ワールドカップが持っているコンテンツの素晴らしさを多くの方々にお届けする一助となれたことを良かったと考えています。

――課題を挙げるとしたら何でしょうか。
「課題」という表現よりは、今回の生中継を経ての「気づき」のほうが近いかもしれませんが、12月5日(月)に行われた日本VSクロアチア戦で、連日多くの皆さまにお楽しみいただいていたこともあり、快適な視聴環境を維持するために必要だと判断した場合にはABEMAへの入場制限を行う旨を事前に告知し、実際に入場制限を行いました。ABEMAで見たいと思ってくださる全ての視聴者の方に、安定した視聴環境にてコンテンツをお楽しみいただくには、現状の日本のインターネット回線では難しいと感じました。配信サービスの現時点での限界が少し見えたように感じたのが正直なところです。視聴環境の限界については、これからの進化でさらにいろいろなことができるようになってくると思いますが、今後そうした進化を経て、より多くの視聴者の方が今見たいと思っているコンテンツを全ての方に提供できるようなインフラ的な存在になっていきたいな、ということはあらためて感じました。
――GMを務めた本田圭佑さんの解説への反響が大きかったですね。「ABEMAの成功は本田さんの解説によるところが大きい」という声もありました。野村さんは、本田さんの解説をどう評価しますか。
「評価する」ということは恐れ多いので感想となりますが、本田さんにしかできない素晴らしい解説をしていただいたことで、ワールドカップもABEMAも、さらには日本全体も盛り上がったと言っても過言ではないと思っております。
本田さんは過去のワールドカップで3大会連続のゴールを決められるなどさまざまなご経験があるのに加えて、ご本人の発する言葉にとても力がある方だと思っており、「ABEMA FIFA ワールドカップ 2022 プロジェクト」のGMへのご就任と解説のオファーを、以前からの友人であった藤田(晋さん。株式会社AbemaTV代表/ABEMA総合プロデューサー)よりさせていただきました。試合中には非常に的確な解説で盛り上げていただき、大変感謝しています。

新たな視聴者に継続視聴を促す「残存プロジェクト」
――スポーツ報知に、藤田さんが、ワールドカップで新たにABEMAの楽しみ方を体験したユーザーに継続視聴してもらうため、「残存プロジェクト」に注力しているという趣旨の記事が出ていました。「残存プロジェクト」とはどんなことですか。
「残存プロジェクト」といっても、何か特別なことをするわけではありません。ワールドカップをきっかけにABEMAをご利用いただいた視聴者の方が継続して利用したくなるようなコンテンツ編成や機能面などにおける充実度を向上させる取り組みを、これまで以上にしっかりと行うことを、社内で「残存プロジェクト」と呼んでいます。
ABEMAは国内唯一の24時間365日放送しているニュース専門チャンネルをはじめ、アニメ、バラエティ、オリジナルの恋愛番組やドラマなど多種多様なジャンルの番組を提供しています。一方でABEMA自体がどういうサービスかまだ十分に伝わっていなかったり、ABEMAを視聴した経験があるものの、一度離れてしまったりした方もいらっしゃると思います。ですので、ワールドカップを通じてまずABEMAを知ってもらい、理解していただくことが重要だと考えていました。そうすれば多種多様な番組の面白さや魅力、ABEMA自体の利便性などを体験しながらご理解いただき、結果として継続して視聴いただける方が増えるのではと考えたからです。
もちろん、ワールドカップ後の今がユーザー数増加に最適なタイミングの1つであることは確かです。例えば、世界最高峰プロサッカー1部リーグである「イングランド プレミアリーグ」2022-23年シーズンの生中継は、ワールドカップ開幕前からスタートしていましたが、ワールドカップを通じて「ABEMAなら、プレミアリーグやスポーツ観戦をこんな風に楽しめるんだ」と知っていただければ、そのまま視聴される方もいらっしゃると思います。そのようにコンテンツの内容や切り口、利便性など、いろいろな側面でABEMAのことを知っていただいて、継続利用につなげられたらと考えています。
――ABEMAの利便性は、具体的にどんな点でしょうか。
ABEMAは「テレビのイノベーション」という考え方からスタートしていて、「場所からの解放」である〝テレビ・スマホ・PCなど好きな場所で視聴可能なマルチデバイス対応”や、「時間からの解放」である〝好きな時に楽しめる見逃し配信、オンデマンド視聴”を提供している点が特徴として挙げられます。その2つの「解放」に伴う機能が常に無料であることは一番大きな利便性だと思います。そのため、そもそもABEMAのコンセプト自体である利便性を、多くの皆さまに知っていただくことが重要だと考えています。
――ネットを見ているとニュースサイトの「ABEMA TIMES」の記事がよく目につきますし、ほかにもYouTubeやTwitter上でABEMAのコンテンツの宣伝を目にします。そういう形でタッチポイントをいくつか設定して、皆さんに知っていただくということでしょうか。
そうですね。世の中のメディア利用状況を見ると、メディアやデバイスもいろいろある中で、コンテンツに対する接し方が変容してきていると感じます。そういう状況を踏まえ、視聴者の日常における導線上でのタッチポイントを複数作り、ABEMAの価値を伝えるマーケティング活動を日々しっかりと行うように心がけています。大切なのは、ユーザー起点の考え方であり、視聴者が接触する機会の多いメディア、デバイス、時間帯などを考慮しながら、最適なコミュニケーションの在り方を考えて、その導線上にABEMAのコンテンツをしっかりと届けることだと考えています。
 (C)AbemaTV, Inc.
(C)AbemaTV, Inc.
競技のポテンシャルを引き出し、競技と一緒に事業成長へ
――わかりました。ワールドカップを終えて、あらためてABEMAに対して感じた可能性や将来性はありますか。
この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。
残り4,224文字
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン