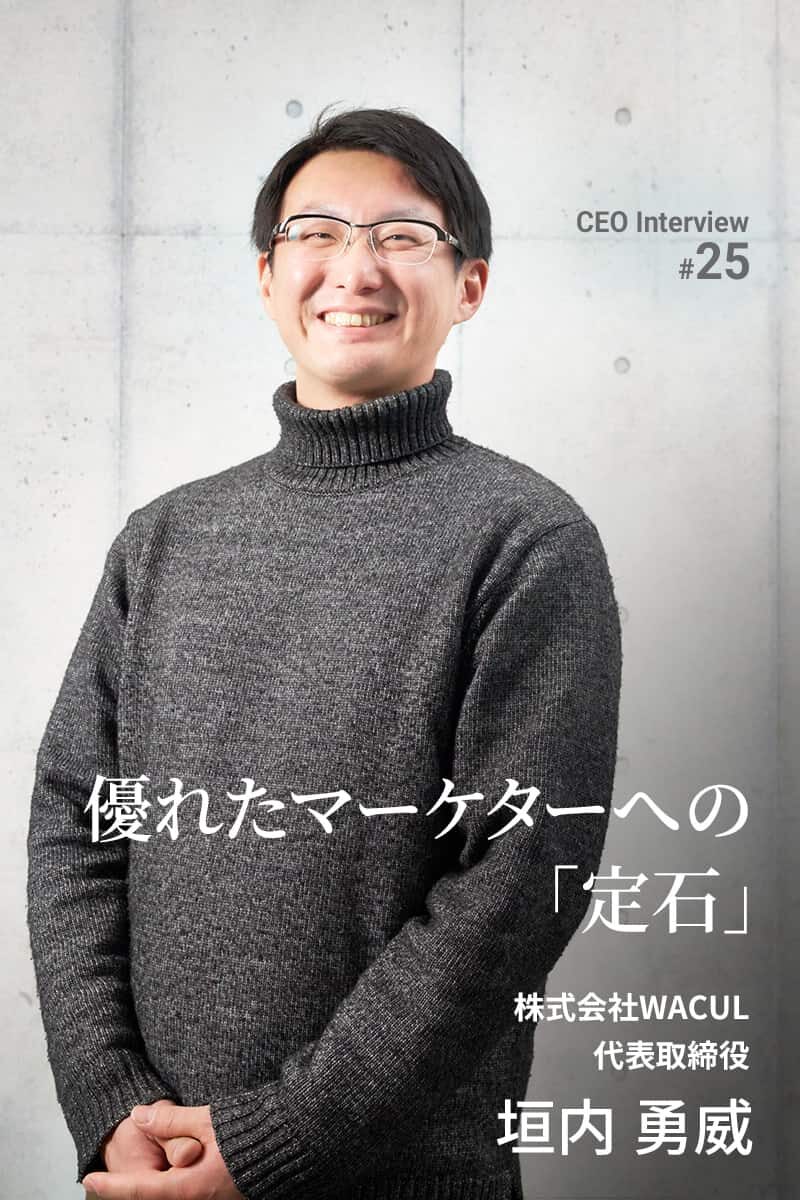WACUL代表取締役・垣内勇威さんの2冊目の著書『BtoBマーケティングの定石』は重版がかかる売れ行きを見せています。
1冊目の著書『デジタルマーケティングの定石』はすでに7刷で、今もコンスタントに売れ続けているとのこと。「売れない」と言われるマーケティング関連本としては異例の好調さと言えるでしょう。
垣内さんがヒットを連発できる秘密は何か。WACULに伺って、話を聞いてきました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、人物撮影:永山 昌克)
目次
どん底の危機から学んだマネジメントの重要性
――デジタルマーケティング関連のインタビューは多くても、垣内さん本人に迫った記事はそれほど見つけられなかったので、そのあたりを聞いていきたいと思います。まず、思い切りさかのぼってどんな少年時代だったのか教えてください。
友達があまりいなかったですね。高校の修学旅行のとき、1人でラーメンを食べたことを覚えています。いじめられていたわけではないですが、大勢の人と関わるのが得意ではないので、今もリアルな友達は2~3人です。ただし、ビジネスでのクライアント対応は得意で、コンサルタントとしてそれなりに自信があります。

――プライベートでは独りぼっちになりがちだけど、ビジネスのコミュニケーションは得意。何が違うのでしょうね。
仕事はゴールが明確だからです。飲み会もアジェンダがあれば参加しますが、アジェンダがないときは会話のネタがすぐなくなるので、「山手線ゲームをしよう」と言います。そうするとゴールとアジェンダが勝手に設定されるので、フリートークのネタを考えなくてもコミュニケーションが成立します。
――飲み会にもアジェンダ…。垣内さんのイメージ通りですね(笑)。新卒でビービットに入り、WACULに転職した経緯については、いろんな記事に出ていますが、成長や学びにつながった経験の中で、忘れられないエピソードはありますか。
WACULは以前、当時の社長とCTOのほか、従業員が何人か辞めたことがあります。そのときはどん底でした。私自身、頭でっかちなところがあり、ビジネスのドライバーは地頭の良さや能力、知識量だと思っていましたが、それだけでは多すぎるハードシングスに対応できず、結局ビジネスはメンタル勝負だと腹落ちしました。今では、何かを継続するために重要なのは、精神的に良い状態をどれだけ保てるかが大きいと考えています。
――なぜ当時、従業員の退職が続いたのですか。
マネジメントができていなかったからです。当たり前ですが、マネジメントとプレイングマネジャーは違います。私自身、それまでマネジメントをされた経験もあまりなかったし、メンバーへのコミュニケーションについても学ばすにやっていたのが良くなかったと思います。
――垣内さんはマネジメントが得意ではないのですか。
得意ではないです。マネジメントもスキルであり、知識なので身に付けられるはずですが、もともと自分のことを組織からはみ出してしまう社会不適合者だから起業していると思っていて、マネジメントも好きではありません。当時の社長らが辞めていった頃は、本当に社員の心が離れていたので、「マネジメントがイケてなくてすみません」と反省のプレゼンをしたことがあります。
それからはマネジメントを身に付けようとしたり、マネジメントの業務ができる人を採用するようにしました。
――そのときはマネジメントの何が良くなかったのですか。
良くなかったというより、マネジメントをしていなかったですね。声を荒らげてパワハラをするわけではなく、単純に目標の数値や目指すコンサルティングの世界に到達していない人に対して、「足りないですね」「それではダメですね」と理詰めで追い詰めるという、再現性の低いことをしていました。「プレイングマネジャー、最初ダメ説」とほぼ同じで、よくある失敗だと思います。
現在は会社として、かなり改善されました。

2冊の「定石」本が人気を呼ぶ背景
――わかりました。次に垣内さんのマーケティング業界における知名度について教えてください。どんなきっかけで名前を知られるようになったのですか。
最初はTwitterだと思います。前職の副社長に勧められて始めたら、意外とウケが良くて、すぐに3,000から5,000フォロワーくらいに達しました。理由は言葉選びがうまくいったことだと思います。私は何かに特別に詳しかったり知見がすごかったりするわけではなく、世の中にある事象を一般の人たちが共感する言葉に変換するのが得意だったようです。さらにその言葉選びが140文字の世界に合っていたことから、フォロワーが増えていったと考えています。
例えば、初期にバズったのは「A/Bテストは無駄」「アトリビューション分析するのは暇人」というツイートで、多くの人が感じていながら明言できなかったことを、自分でしっかり立証して確信があるからと言い切ったところ、共感してくれるフォロワーがたくさん現れました。
――わざと言い切っているのかと思ったら、確信があるのですね。
確信もありますし、私はそもそもゼロイチしか言いません。心理テストで「0から10の中から選んでください」と言われたら、0か10を選びます。コンサルティングのときもクライアントは私に言い切ることを求めているので、本当にどちらでもいいとき以外は、51対49の確率のときでも「51のほうです」とスタンスを取るようにしています。
――「違ったじゃないですか」と言われないですか。
「そうですか」「なぜ違ったのか考えましょうか」と言うだけです。
――垣内さんが再三主張しているにもかかわらず、A/Bテストは今も多くの会社で行われています。
大手企業が「AのほうがBより良い」ということの社内説得のためにやるのであれば、やってもいいとは思います。経営層を説得するのに必要であれば、利用すればいい。しかし、ベンチャー企業でそこまで社内の説得に労力を使わなくて済むならしなくていいし、まじめに科学検証しようと思っているのだとしたら時間の無駄です。
――わかりました。次に2冊の著書について伺います。2冊とも「定石」というのがすごいですよね。
ひたすら偉そうなことを言ってみるという(笑)
――それが垣内さんの芸風だと理解している人が多そうです。その証拠に1冊目の『デジタルマーケティングの定石』が7刷、2冊目の『BtoBマーケティングの定石』も重版がかかった、と。担当編集者は社長賞を受賞したとのこと、すごいですね。なぜ売れたのだと思いますか。
Twitterで何がウケるのか、ある程度わかっていたからだと思います。デジタルマーケティングやBtoBマーケティングの従事者が何を期待していて、どこに困っているかをわかっていたので、そこに刺さるように書きました。
今も継続的に買ってくださる方がいらっしゃるのは、新しくWebの部署に入ってきた人に「この本を読んでおいて」と教科書的に引き継がれているからではないかと想像しています。もしそうならうれしいですね。

デジタルマーケティングの将来性とマーケターがすべきこと
――デジタルマーケティングはこれからも発展していく未来のある領域ですか。
この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。
残り5,047文字
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン