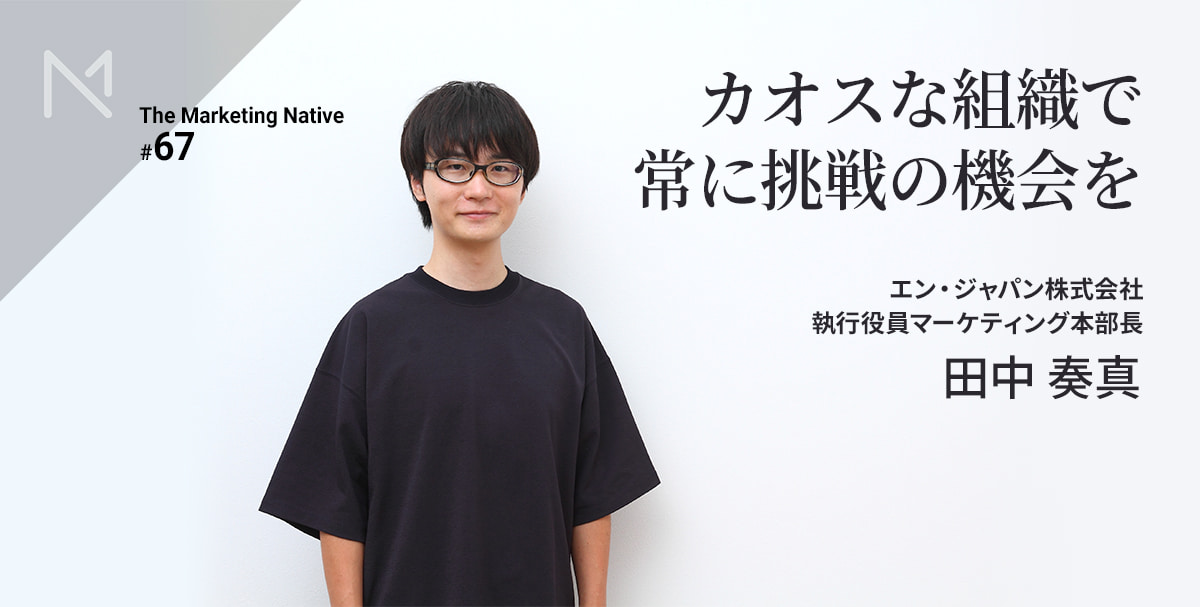全国で1,500店舗以上(グループ全体)を展開するサンドラッグ。医薬品はもちろん、食品や日用品の品揃えも充実し、つい毎日立ち寄ってしまう人もいるでしょう。
サンドラッグはEC事業にも注力しています。その先頭に立って事業を推進するのがAmazonJapan出身で、サンドラッグでは執行役員 EC事業部 事業長を務める田丸知加さんです。
入社当時、課題を多く抱えていたという同社のEC事業に、Amazonで培った知見を活かしてDXを推進。顧客満足度の大幅な向上に成功しました。その方法とは?
今回はサンドラッグの田丸知加さんに話を聞きました。
(取材:Marketing Native編集長・佐藤 綾美、文:和泉 ゆかり、撮影:矢島 宏樹、構成:編集部・早川 巧)
※肩書、内容などは記事公開時点のものです。
目次
Amazon Japanの黎明期に“DX”を推進
――イベントでお話を伺い、とても面白かったので、以前から取材させていただきたいと思っていました。まずは現在までのキャリアを教えてください。
日本の大手通信会社を経て、2003年にAmazon Japanへ入社しました。当時のAmazon Japanは社員数が100人にも満たず、Webサイトの更新も1日1回、商品情報は手作業で入力していたような時代です。在籍中はマーチャンダイジング、発注管理、マーケティング、販促活動、契約業務など小売部門の全カテゴリーにおいて、さまざまな業務効率化やシステム化を推進してきました。

――まさにAmazon Japanの黎明期から参画し、デジタルの基盤を作られたのですね。
まだDXという言葉も知られていないような時代でしたが、プロセスをシステム化し、業務改革を進めていく取り組みは、振り返ると、まさにDXそのものだったと感じます。
Amazon Japanに16年ほど在籍した後、セブン&アイ・ホールディングスにジョイン。デジタル戦略企画部長として、グループ企業全体のデジタル戦略や新規事業の立案を担当しました。その後、当時Walmartの傘下にあった合同会社西友に参画、楽天西友ネットスーパーと西友のオムニチャネル事業に携わりました。
現職のサンドラッグに入社したのは2021年11月です。サンドラッグは、ドラッグストア業界の中でもEC事業に早くから注力してきました。2021年から5カ年の中長期計画においても、EC事業は重要な戦略の柱として位置づけられており、私が事業長を務めるEC事業部は社長直下の組織となっています。
私が入社したのはコロナ禍ということもあり、EC事業推進の重要性が一層高いときでした。医薬品のインターネット販売市場の急拡大も見られた時期です。さらなる成長のためには、これまでの仕組みややり方を変革する必要があり、デジタル化やECにさらに注力すべきだとする機運が高まっていました。そんなサンドラッグに入社を決めたのは、私がそれまでに培ってきた経験を活かせるのではないかと考えたからです。また、ドラッグストアは、医薬品というお客さまの人生に深く関わる重要な商材を提供しています。そのような事業に携わることで、会社とともに私自身も成長できると思いました。
現在は日々の業務と並行して、日本オムニチャネル協会のフェローを務めているほか、セミナーで講演をしたり、インタビュー取材を受けたりする活動も行っています。
――お話を伺っていると、小売企業の中でも特にデジタルやEC領域でキャリアを積んでいますが、どのような点に魅了されているのでしょうか。
大きな改善の余地があると感じるからです。Amazon Japanに在籍していた頃、アメリカで利便性向上や業務改善が次々と実現する様子を目の当たりにし、日本との技術格差を強く実感したことが背景にあります。

DXで直面した、変化に保守的な社員とのコミュニケーション
――サンドラッグ入社後、リテールDXを進めるうえで感じた課題はありましたか。
サンドラッグはEC事業に早くから力を入れて取り組んではいたものの、実際は多くの課題を抱えていました。商品の発注業務や商品登録、お客さまへの対応など、ほぼすべての業務が手作業で行われていたのです。組織やシステム、運用、さらには教育について、改善が必要な課題が山積していました。
――具体的にどこから着手したのですか。
まず行ったのは知識の共有です。当時のサンドラッグ社内にはデジタル専門人材が少ない状況でした。システム部門も主にインフラ寄りの知見は豊富にあっても、マーケティングやEC、顧客データベースといったデジタル領域に精通した人材は限られていました。
そこで1~2カ月程度かけて、EC事業部はもちろん、経営層や主要な関係部署のステークホルダーに対して、わかりやすい言葉で丁寧に説明し、理解を深めてもらう啓蒙活動から始めました。なぜなら実際の業務では物流、商品管理、販促など、さまざまな部署との連携が不可欠であり、共通の知識に基づく共通言語が必要だからです。
――DXを推進するとなると、カタカナ用語が多く、慣れていない方には難しく感じそうです。
カタカナ用語をできるだけわかりやすく日本語で伝えることは、Amazon Japan時代に数多く経験してきました。当時は多くの取引先企業にとってデジタル環境での商品展開は未知の領域であり、例えば商品画像に関して「1,000ピクセル以上のJPEG形式で」と説明しても、そもそも「ピクセル」「JPEG」などの言葉を知らず、伝わらない状態でした
また、当時のAmazon Japanにはデジタル技術に詳しい人材も少なかったため、アメリカ本社からの技術的な指示や要件を「こういうスペックで」などとそのままカタカナ用語で伝えても、理解を得ることは容易ではありませんでした。そのため、できるだけカタカナ用語を避け、わかりやすい日本語に置き換えて説明することを徹底しました。現在の業務で問題なくコミュニケーションができているのは、当時わかりやすく説明することを繰り返した結果、スキルが身に付いたのだと思います。

――田丸さんが入社され約3年が経ちました。リテールDXにおいてメインとなる取り組み内容としては、ECサイト(サンドラッグ Online Store)の全面リニューアルが挙げられると思いますが、どのように進めたのでしょうか。
|
この記事は会員限定です。無料の会員に登録すると、続きをお読みいただけます。 ・サンドラッグ Online Storeの競争優位性 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン