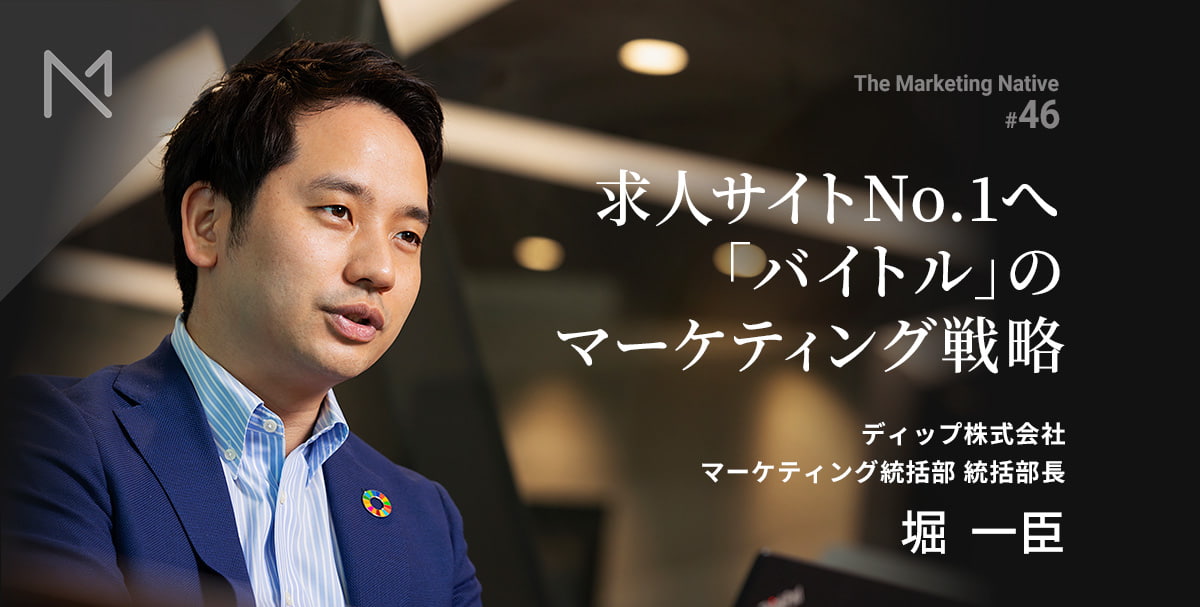訪問先のオフィスビルや病院の1階に入っていると、ちょっとうれしいタリーズコーヒー。1997年の1号店オープンから25年。周年記念の大型キャンペーンのほか、新型コロナウイルス感染症の影響で苦戦の続く飲食業界にあって、業績回復の兆しが見られることでも注目されています。
とはいえ、コーヒー業界は多様化しており、競争は過熱。カフェチェーンだけでなく、缶コーヒーもあれば、ペットボトルのコーヒーもあり、コンビニのレジ横コーヒーも美味しいし、昔ながらの喫茶店も健在。さらに最近では、スペシャルティコーヒーのスタートアップも注目されています。
数多くの選択肢がある中で、顧客にタリーズコーヒーを選んでもらうために、タリーズではどんなマーケティングを行っているのでしょうか。今回はタリーズコーヒージャパン株式会社 マーケティング本部 グループ長・工藤和幸さんに話を聞きました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)
目次
タリーズが「コーヒー豆に自信がある」と胸を張る背景
――工藤さんはマーケティング本部のグループ長を務めているとのこと。まず、これまでのキャリアや日頃の仕事内容を教えてください。
タリーズに転職したのが2003年秋。2年ほど店舗経験をした後、営業推進グループを経てマーケティングに携わり始めました。マーケティングの経験は15年ほどになります。
現在はマーケティング本部「ドリンク・フード・デジタルマーケティング担当」グループ長として、店頭で販売する飲み物と食べ物の商品企画や、デジタルコミュニケーション周り全般を担当しています。

――タリーズは創業25周年。この25年で、日本人にどんな価値をもたらしたとお考えですか。
タリーズは店舗数が約760店舗で、カフェ業界4番手(※1)。その規模で社会にどれだけ影響を与えられているのかはわかりませんが、自信を持って言えるのは、一貫して美味しいコーヒーをお届けしていることです。
※1
店舗数は1位:スターバックスコーヒー、2位:ドトールコーヒー、3位:コメダ珈琲、4位:タリーズコーヒー、5位:サンマルクカフェの順。
――「美味しいコーヒー」といっても、各社皆、「自社のコーヒーが一番美味しい」と考えていると思います。
我々がお客さまに提供しているのは「スペシャルティコーヒー」(※2)です。
コーヒー業界は少し複雑です。コーヒー豆は先物取引ですし、昔は商社が在庫で保管していました。缶コーヒーを作るときも商社の在庫から豆の銘柄を選んでいたのです。
それに対してスペシャルティコーヒーであるタリーズは、コーヒー豆の生産国に定期的に足を運び、真に美味しいコーヒーを生み出すべく、農家の方々と一緒に汗を流しながら品質の高いコーヒーの生産に取り組んできました。今も「生産国との懸け橋になる」という思い入れを、とても大切にしています。
もちろん、嗜好品なので好き嫌いはあると思いますが、我々が品質などの点で不採用にした豆を他のカフェチェーンで販売していることがありますので、お客さまにはどちらが美味しいコーヒーか、必ずわかっていただけると考えています。
近年、コーヒーの生産地、生産者との良好な関係性を謳う企業は増えていますが、我々は15年ほど前から先駆者として取り組み、情熱を持って美味しいコーヒーをお届けしてきました。そこが他のカフェチェーンとの違いであると胸を張れる要素の一つです。
※2
「スペシャルティコーヒーの定義」(一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会)
https://scaj.org/about/specialty-coffee
――私もコーヒー豆生産国との関係性のような価値観を最近知ったのですが、タリーズがずっと取り組んできたとは知りませんでした。これまでもアピールしてきたのでしょうか。
はい、言葉にして伝えてきました。ただ、お客さまに提供されるコーヒーはすでに液体になった商品の状態であることが多く、これまでは農家の方々との取り組みなどがリアリティを持って受け止められていなかったと思います。最近、SDGsなどが注目されたり、スペシャルティコーヒーの存在がクローズアップされたりする中で、ようやく価値が広がってきたと感じています。

店舗への集客に効果的な「コラボ企画」などの話題作り
――顧客層はどうですか。年代や性別で明確な違いはありますか。
もともとビジネス街を中心に出店していましたので、ビジネスパーソン向けから始まりました。現在では平準化できています。
――工藤さんが担うタリーズのマーケティングとはどのような仕事ですか。
店舗への集客と、店内における顧客体験の最大化が基本です。「ご飯を食べる」欲求がほぼ絶対発生するのに対して、「コーヒーを飲む」欲求は、嗜好品なので、食事と比べると小さめです。しかも、インスタントコーヒーもあれば、缶コーヒーもペットボトルのコーヒーもあり、選ばなければ簡単にコーヒーを飲める環境が整っています。その状況で、より多くのお客さまにタリーズを選んでいただくにはどうすれば良いか、それをさまざまに考えて、実践していくのがタリーズのマーケティングの役割です。
――タリーズの存在は、ビジネスパーソンを中心によく知られていると思うのですが、現在4番手のシェアを変えていくために、どんなことが必要だとお考えですか。
この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。
残り6,067文字
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン