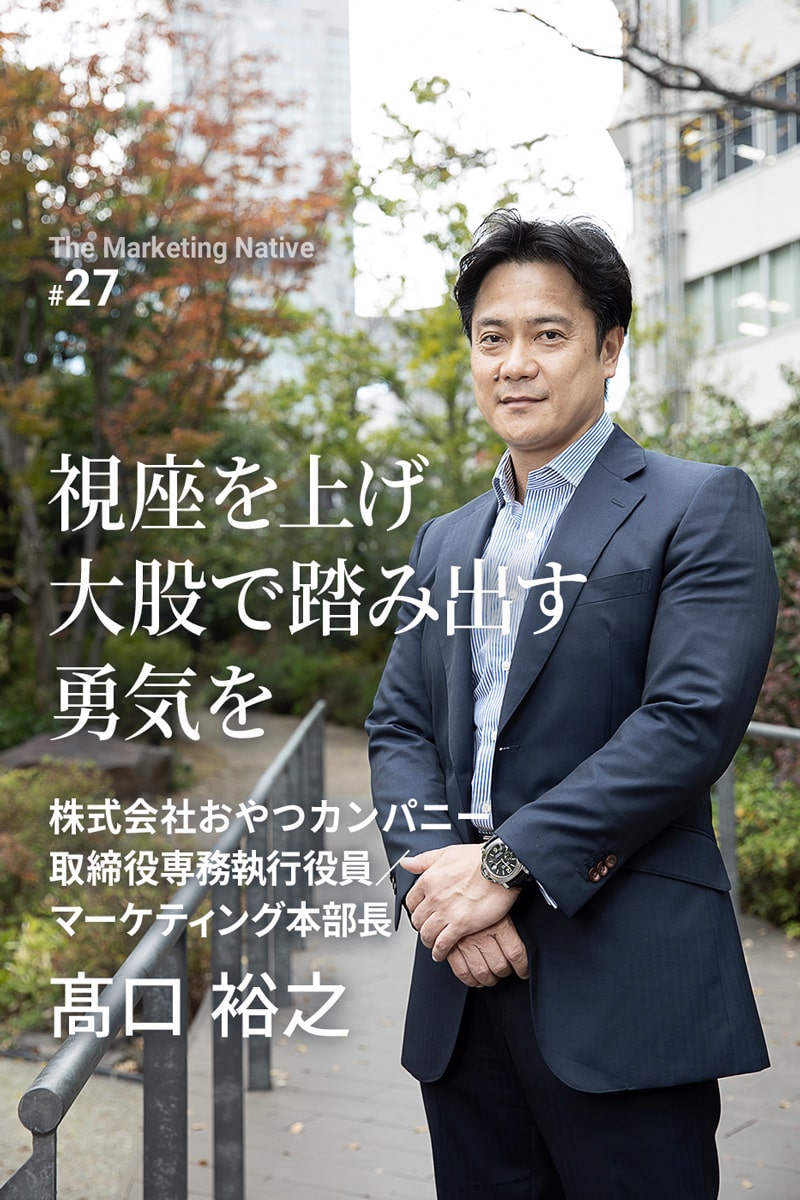おやつカンパニー取締役専務執行役員/マーケティング本部長・髙口裕之さんのインタビュー後編をお届けします。
後編では、組織をプロダクトアウトからマーケットインの思考方法に変えることの重要性と難しさ、さらにはこれから伸びる可能性の少ない市場環境にいるマーケターが生き残るためにすべきことをお聞きしました。
ぜひご一読をお願いします。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、写真:矢島 宏樹)
※前編はこちら。
※肩書、内容などは記事公開時点のものです。
目次
全ての戦略をマーケティング・ファーストで
――組織作りの話をお聞きします。髙口さんがジョインするまでマーケティングの部署はなかったとのことですが、その後マーケティングの考え方は社内に浸透していますか。
正直、まだイメージには遠いのが現状です。しかし、「マーケティングとは何か?」「マーケティングの価値とは何か?」を少しずつ理解している社員が増えてきていると思います。
ただ、私としては全ての戦略をマーケティング・ファーストで考える組織にしたいのですが、どうしてもまだプロダクトアウトの考え方が残っています。

もちろん、そこにも良い点はあるのですが、中途半端な形で進めても、おそらくあまり変わらないと思います。変えるのであれば一気に、根本から変えたいのが率直なところです。それで一時期は混乱しますが、前職での経験上、その後は大きく伸びると確信しています。
グローバルで成功している多くのFMCG企業同様、マーケティングの下に技術セクションをつける形にしたいのですが、出来上がった商品を正当化する作業がやはりまだ何割か存在します。私はそれをゼロにしたい。ロジックのつながらない、曖昧なことはなくして、全部マーケットインで説明のつく商品にし、そこに全てのリソースを投入して勝負をかける方法を描いていきたいというのが経験を通じて過去から変わらない私の考え方です。
――今はゆっくりと組織を理想の形へと変えている感じですか。
ゆっくりですが、「BODY STAR」は全社的なコンセンサスを取り、いよいよアクセルを踏んで商品が出ていくわけですから、大きな進歩です。これが数字になれば一気にモーメントが動きだすと思います。やはり成功体験、実績を作って証明しないと人は容易に動きません。

基本習得の大切さとメタ認知の重要性
|
この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン