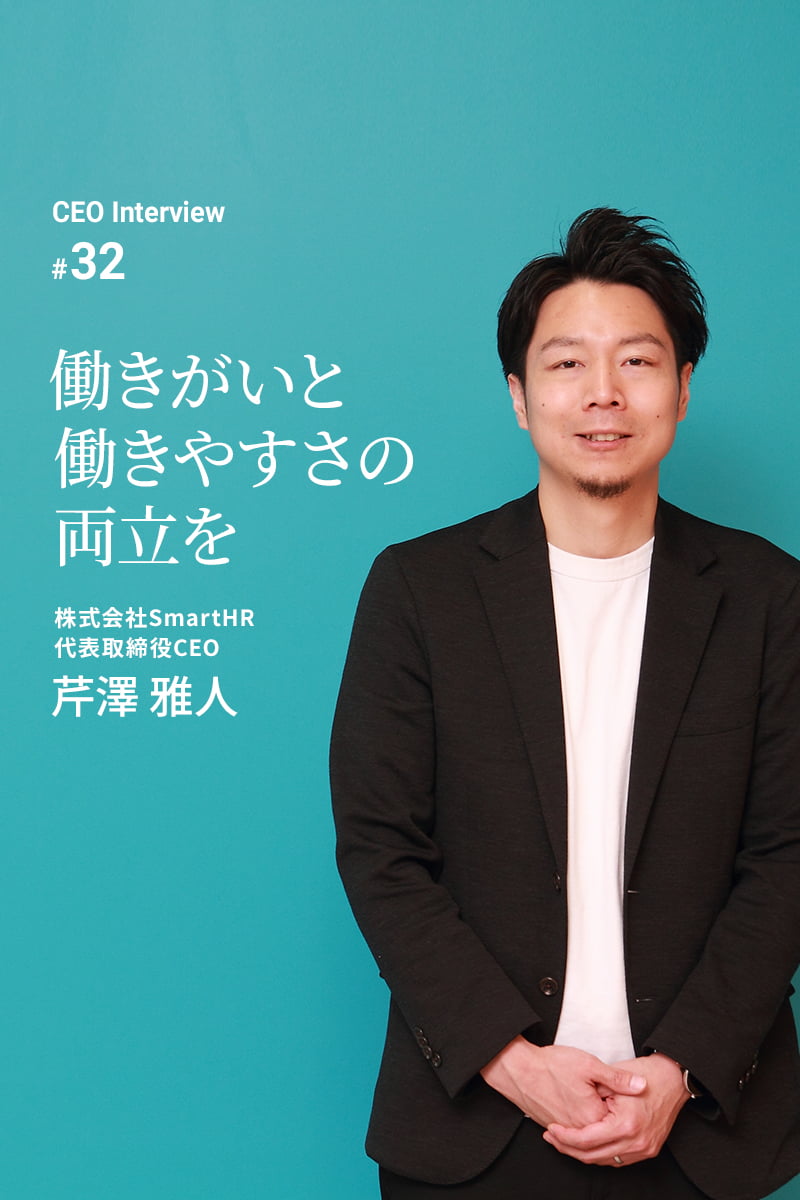HRテクノロジーのリーディングカンパニー、SmartHR。勤務先が導入していて、年末調整などの際に大いに役立っているという人も多いと思います。
SmartHRは企業としての急成長ぶりも有名で、2021年6月に時価総額約1,700億円でシリーズDラウンドの資金調達を行い ユニコーン企業となり、2024年7月には「日本スタートアップ大賞(内閣総理大臣賞) 」にも輝きました。
SmartHRの指揮を執るのが2022年1月にCEOに就任した芹澤雅人さんです。
今回はSmartHR 代表取締役CEOの芹澤雅人さんをインタビュー、芹澤さんの人物像や、従業員数が約1,400人になったSmartHRをどのように運営しているのかなどについて話を聞きました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:海保 竜平)
目次
マネジメントに向いている人、向いていない人
――芹澤さんはSmartHRの創業初期にエンジニアとして入社し、今は従業員数約1,400人となったSmartHRでCEOを務めていらっしゃいます。なかなか経験できるキャリアではないと思いますが、ご自身では自分のどんなところが評価されてCEOに就任できたとお考えですか。入社当初から「キミは見どころがあるから社長候補だ」と言われていたのでしょうか。
そのようなことは言われていないですね。前任の宮田(昇始・SmartHR創業者、現Nstock代表取締役)さんが社長を退任されるとき、私はCTOで、ほかにCOOとCFOを加えた計3人が社長候補になっていました。3人で話し合ったり、取締役会で1人ずつ、「どんな会社にしていきたいか」などCEO就任後の抱負や計画についてプレゼンをしたりしたのですが、私はカルチャーの話をしました。

SmartHRが優れたプロダクトをスピード感をもって作成し、販売できているのは組織能力が高いからです。その組織能力の高さを裏打ちしているのがカルチャーであり、カルチャーを宮田さんから引き継いで、さらに良くしていきたいという話をしたところ、評価を頂き、CEOに選ばれました。創業初期から宮田さんと一緒に事業やプロダクトだけでなく、組織のカルチャーも含めて会社を一緒につくってきたところが大きかったと思います。
――ご自身はマネジメントにもともと向いている性格だと思いますか。
いえ、もともとSmartHRに入社したときは向いていないと思っていました。当時は20代で、自分のエンジニアとしての腕をもっと磨いてプレーヤーとして突出したい気持ちがまだ強く、人に気を配る余裕があるくらいなら、自分の成長にリソースを当てたいと考えていました。前職でも少しマネジメントをしていましたが、そのときも楽しみを見いだせなかったため、SmartHRでもなるべく避けたかったのが正直な気持ちでした。
――マネジメントを身につけるために努力したことはありますか。
はい、マネジメントの「基本(きほん)」の「き」からしっかりと勉強しました。結局SmartHRでもマネジメントをするとなったときに、前職時代のように失敗したくなかったからです。日本では、プレーヤーとして活躍していた人が、会社からマネージャー就任を打診され、そのまま所属する部門のマネジメントを任されるというパターンがよくあります。その場合、マネジメントの基本を知らないまま、自分が上司からされていたことを見よう見まねで、とりあえず始めてみるという人が少なくないようです。
それでは前職時代のようにうまくいかない可能性があると思い、私はマネジメントの書籍を数冊読み、基礎知識を蓄えて、守破離の守を徹底することを意識しました。1on1や評価方法など、マネジメントは歴史も古く、体系的にも整理されています。我流にならないよう勉強して、マネジメントの基礎をしっかりと押さえてから本格的に取り組んだことは良かったと思います。
――ご自身がエンジニアなので、最初はエンジニア組織のマネジメントを担当した、と。エンジニアは腕に自信のあるタイプが多く、マネジメントの難度が高いと聞いたことがあります。
確かに、20年ほど前の感覚では、職人気質のスーパーエンジニアがすごく頑張ってプロダクトを作るという世界だった気がします。しかし、この10年ほどはレベルが大きく上がって時代も変わり、技術がコモディティ化してきました。その結果、エンジニアの組織に何が起きたかというと、チームワークが重視されるようになったのです。近年は「エンジニアリングはチームワーク」という考え方が前提になっていて、いかにチームビルドするかが研究されています。
私もエンジニアリングのマネージャーをしたときに、エンジニアの組織論を学びましたが、当時すでにレベルの高い組織論だと感じました。今ではエンジニアそれぞれが「チームで協力して進める」という感覚が強くなっており、私が担当していた当時も大きな苦労はなかったと思います。
――従業員をマネジメントに引き上げる際に、向き・不向きの選別はどこで判断しますか。
良い悪いではなく、向き・不向きはどうしてもあります。私が従業員に対してマネジメント向きだと思うポイントは大きく2つ。1つは人の感情の動きに敏感なことです。機微を察するのに長けている人はやはりマネジメントに向いています。
もう1つは、利他的な気持ちが強く、いわゆる「ギバー」(Giver、与える人)であること。自分のことより人を優先して動けるタイプは向いていると思います。
この2つが欠けた人がマネジメントに携わっていると、次第にストレスが大きくなっていき、うまくいかないことが多い気がします。

新卒採用と育成が、従業員の成長意欲を刺激
|
この記事は会員限定です。無料の会員に登録すると、続きをお読みいただけます。 ・実力主義と働きやすさの両立 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン