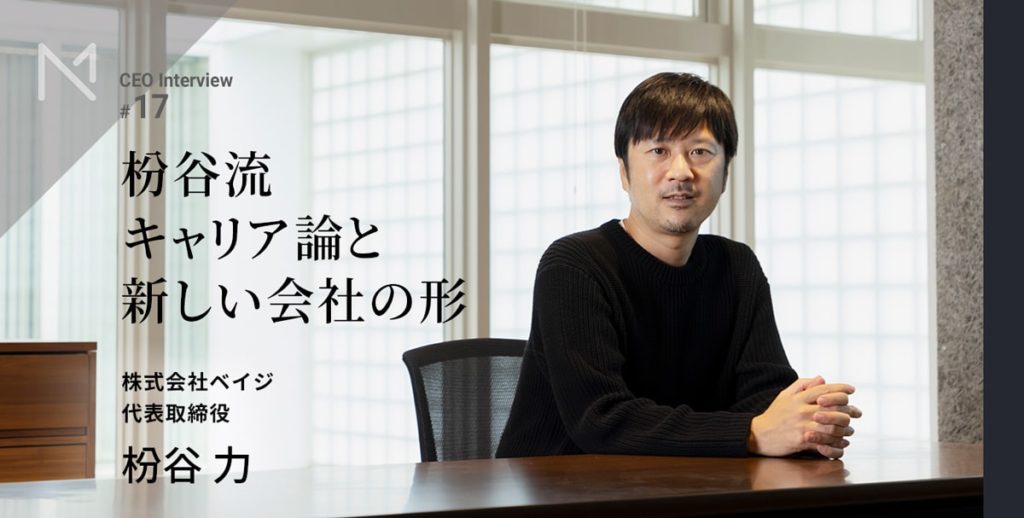ベイジ代表の枌谷力さんが昨年(2021年)11月に投稿したツイートに驚きました。社内勉強会にゲストを招いてキャリアの話をすることがあり、社員にオススメの転職本を紹介することもあるというのです。
ツイートには「本心は他の会社に転職してほしくない」とありますが、会社の代表が転職について想起させる本を勧めるなど、あまり聞いたことがありません。その真意は何か。枌谷さんのところに伺うと、ツイートの内容以上に驚くべき話を聞くことができました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)
※ベイジ社内勉強会資料は記事の最後にあります。
目次
綺麗事でないキャリア論に真剣に向き合うべき理由
――このツイートを拝見し、驚きました。社内勉強会でゲストを招いてキャリアの話をしたり、会社の代表自らおすすめの「転職本」を紹介したりするのは異例だと思います。社員が外部の人と接触するのを嫌ったり、囲い込もうとしたりする代表の話は聞きますが、枌谷さんはいつから、どんなきっかけでキャリアの話をするようになったのですか。
「いつから」と正確な時期があるわけではありません。デザイナーやエンジニアとの1on1で仕事や将来の話をすると、自然とキャリアの話になることがよくあります。社員は5年後、10年後、あるいは20年後かもしれませんが、いつかは会社を辞めるわけです。現在もすぐそばにベイジ以外の働く選択肢があります。その事実に触れないまま、ベイジにずっと所属している前提で話をしても、綺麗事に聞こえるおそれがあります。「ずっとこの会社にいるつもりはないのに」と思っているかもしれません。それならば一層、いつか辞めることを前提に、一般的なキャリア論に触れて話したほうが、今の仕事に意義を見いだし、ベイジの中で何を学ぶべきかをしっかり考えるきっかけになる気がしています。

――大胆に踏み込みましたね。すごいと思うと同時に、いくら会社の代表でも、そこまで社員の人生の面倒を見てあげないといけないのかと思ってしまいます。
「社員の人生の面倒を見る」というほどに大袈裟には捉えていません。でも、社員のキャリア形成に会社が大きく関係するのは事実ですよね。それはある意味、「UX」と考え方が似ているかもしれません。プロダクトのデザインを考えるときに、ユーザー体験全体で捉えることが大事なように、今の会社で働く意義を考えるときに、社員の人生、ライフエクスペリエンスから落とし込まないと説得力が生まれない気がします。
――なるほど。ただ、キャリアをよく考えた結果、辞めるという決断をする社員もいると思います。採用を積極的に行う一方で、せっかく大切に育てた社員が辞めていくのはつらいと私が経営者なら感じるでしょう。だから社員が外部と接触するのを嫌がる代表も少なくありません。枌谷さんも大切に育てた社員に辞められると、つらいという感情にならないですか。
つらくないと言ったら嘘になりますが、辞める辞めないは本人の自由ですからね。辞めてほしくない人に辞められたとしたら、それは会社に何かが足りなかったということなので、制度を整えたり改善したりするしかありません。人がスイッチするのは市場原理ですし、それが嫌なら自分たちを魅力的にするしかない。この考え方はマーケティングと同じですね。もちろん、時代背景もあります。外部との接触を制限したところで、SNSを見れば他社の情報は容易に入ってきますから。情報統制などできない時代です。それならば、「それでもベイジにいたらこんなに良いことがあるよ」と、客観的な視点からフェアな話をするのが、採用や育成における正攻法だと思うのです。
――それだけ自分の会社に自信があるということですか。
社員がベイジで働き続けたくなるにはどうすればいいか、とずっと考えて仕組み作りをしています。もしも自信がなく不安な部分があるなら、それは仕組みを改善するしかない。このように仕組み作りに注力しているのは、「辞められたら嫌だ」という、私の恐怖心から来ている部分もありますね。
――社員が辞めることに対する恐怖心自体はあるのですね。
もちろん、「辞めてしまったらどうしよう」という怖さは常にありますよ。月曜の朝イチに「お話があるのですが」とチャットが来たら、それは怖いですよね。ただ、社員が辞めようと考えるのは、何かの問題が露呈しているからだと思うんです。それに対して私ができることは、その問題を見つけて解決していくだけ。社員が辞める怖さに立ち向かう方法は、情報統制ではなく、会社の仕組みを整えたり、キャリアに関する一般的な事実を伝えたりして、ベイジでの仕事に意義づけをし、魅力を感じてもらうこと。これしかないと思っています。

クリエイターが陥りがちなスキルベースの罠
――社内勉強会にゲストを招いてお話をしていただいたとのことですが、どんな方をお招きしたのですか。
社内勉強会におけるゲストトークの取り組みは、昨年(2021年)から月1~2回のペースで開催していまして、キャリアについては3部作の形で行いました。1回目が私のキャリア論、2回目はインサイトフォースの山口義宏さん、3回目がミルボンの竹渕祥平さんです。
私と山口さんの考え方はかなり似ています。ただ、私の場合、よりクリエイターの実務を前提としたキャリア論について話しました。具体的には、クリエイターのキャリア形成における以下の3つのタイプの話です。
- スキルベース
- ポジショニングベース
- コミュニケーションベース
|
この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。 ・20代のうちに貯めておきたい4つの「資産」 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン