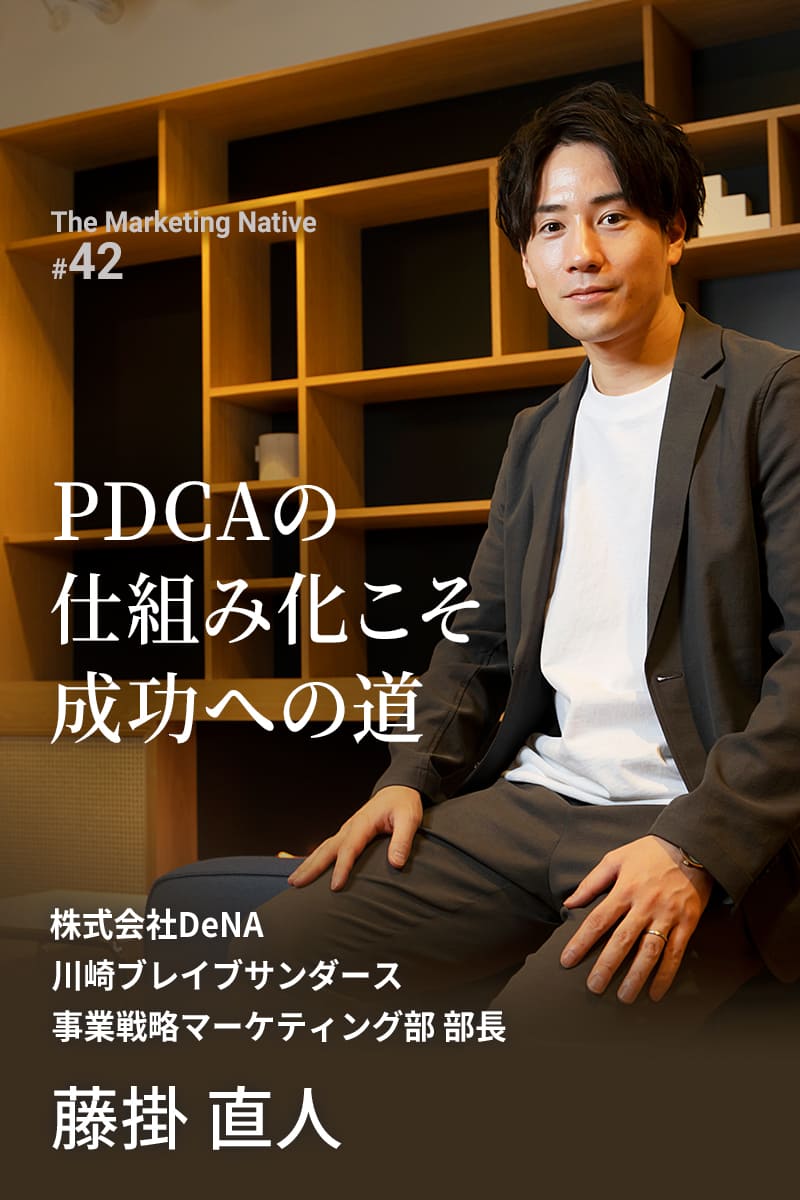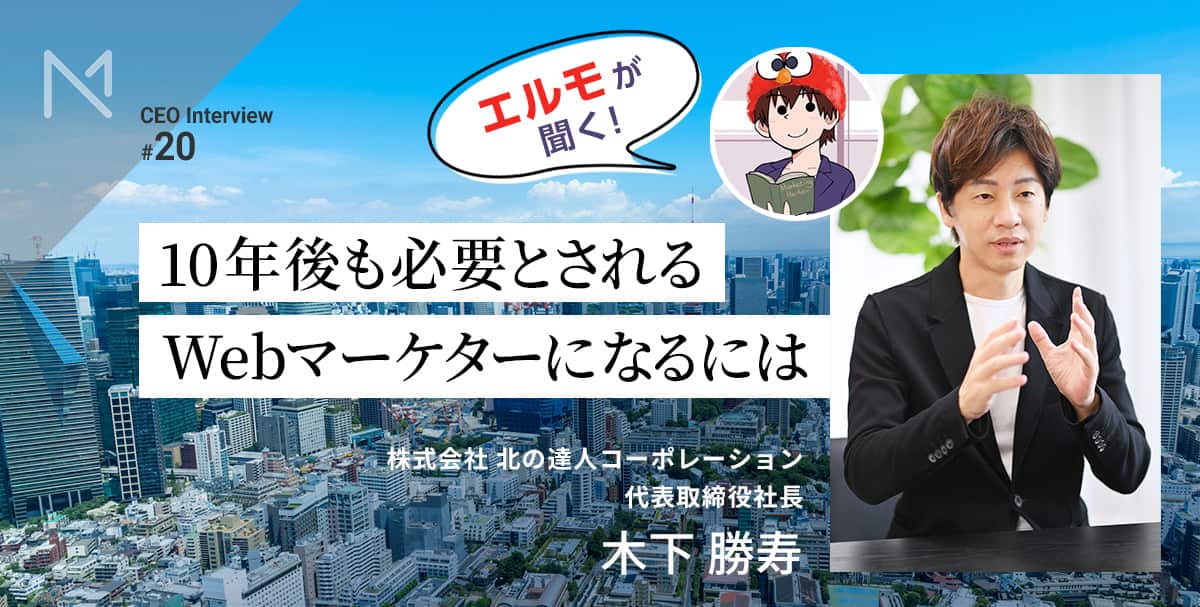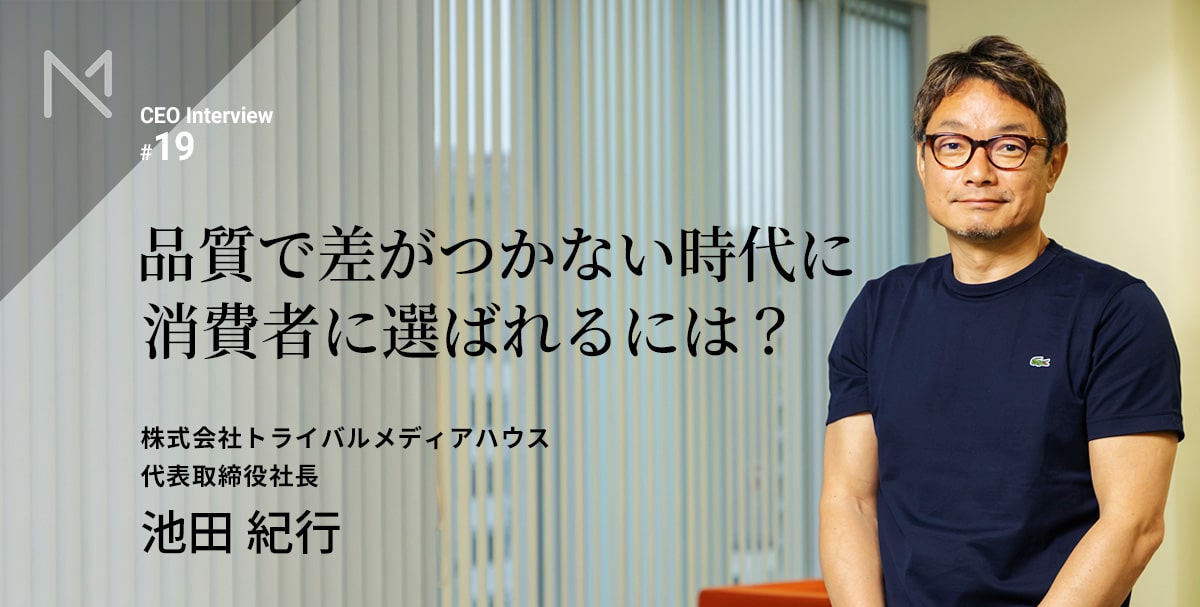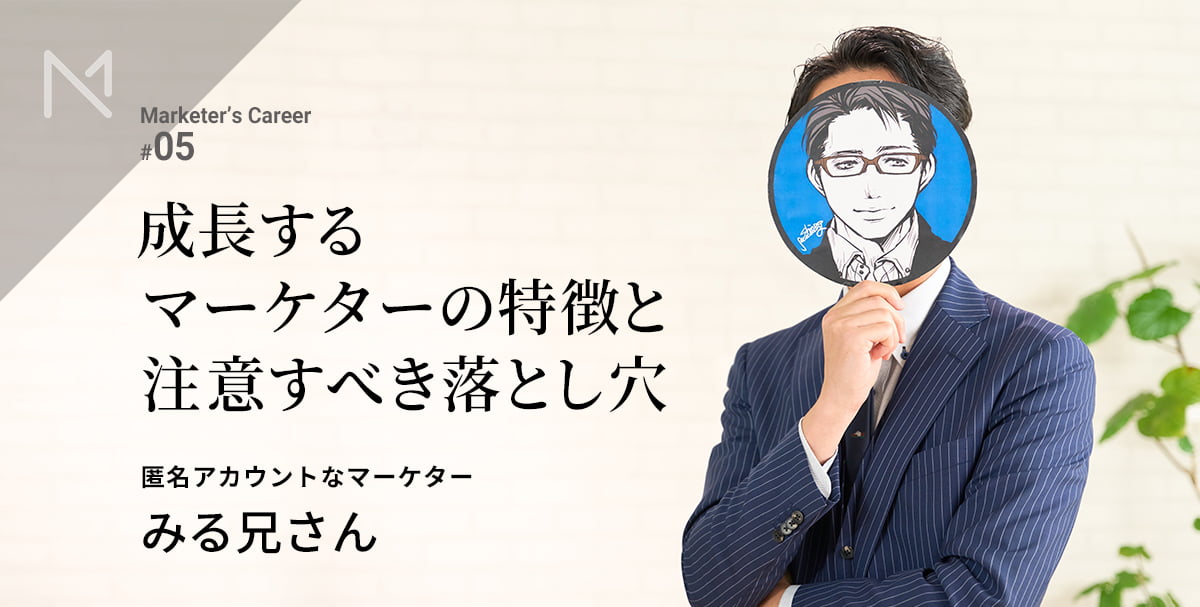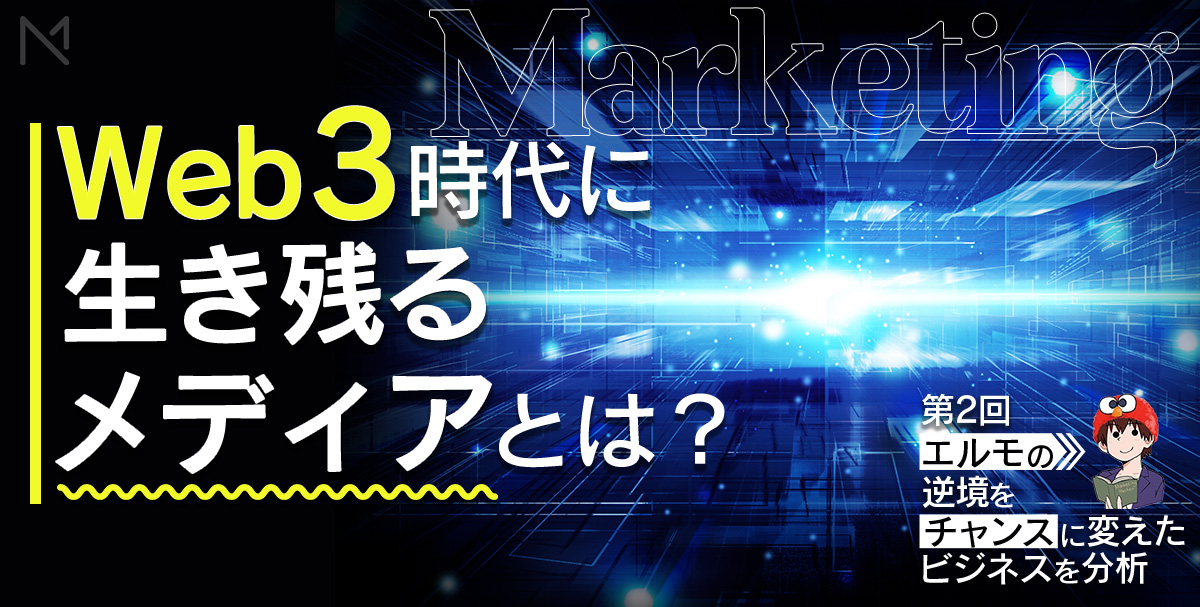プロバスケットボール「B.LEAGUE」(以下「Bリーグ」)といっても、プロ野球のセ・パ両リーグやサッカーJリーグと比べて認知度は高くなく、試合の観戦経験のある人もまだ少数派かもしれません。
ところが、そのBリーグにYouTubeチャンネル登録者数が JリーグとBリーグを含めて1位、TikTokフォロワー数は読売ジャイアンツに次ぐ国内プロスポーツクラブ2位、観客動員数もBリーグ1位(※)という高い成果をマーケティングなどの施策によって達成したクラブがあります。それが神奈川県川崎市をホームタウンとする「川崎ブレイブサンダース」(以下「ブレイブサンダース」)です。
一体どのような手法でこのような実績を上げることができたのでしょうか。今回はブレイブサンダースを運営する株式会社DeNA川崎ブレイブサンダースで事業戦略マーケティング部 部長を務める藤掛直人さんに話を聞きました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)
※数字はいずれも2022年4月時点。観客動員数1位は2020−21シーズンの1試合平均来場者数の結果。
目次
無限の広がりを感じたファンづくりの可能性
――藤掛さんの著書『ファンをつくる力』を読んで、初めてブレイブサンダースの存在を知りました。藤掛さんはどんなきっかけでクラブと関わるようになったのですか。
DeNAでプロデューサーをしていたゲーム事業部の業務が一段落して、次のチャレンジの場を探していたときに、社内で新しいスポーツ事業への参入を検討していると聞いて手を挙げたのがきっかけです。小中高とバスケをしていたこともあり、いつかはバスケに関わる事業を手掛けたいと思っていましたし、リアルなエンタメビジネスへの強い興味関心も持っていたので、「ぜひ自分がやりたい」と立候補して、当時の運営会社(東芝)からの事業承継交渉から入りました。

――ブレイブサンダースのマーケティングに携わり始めて、真っ先に着手した課題は何ですか。
リアルビジネスなので、デジタルサービスに比べてデータが圧倒的に不足していました。そのため、ゲーム事業部のように集めたデータから施策を立案し、高速でPDCAを回せる仕組みづくりを目指して、データ収集から着手しました。
具体的には、試合ごとにアンケートを細かく取って定量・定性両方でデータが蓄積される状態を作り、集客や体験価値向上のために実行している各施策の効果測定を行って、毎回PDCAを回せるようにしました。
もう1つはチケット販売方法の一本化です。もともとはローチケ(ローソンチケット)やe+(イープラス)などプレイガイドによる代理販売を活用していたのですが、販路拡大のメリットがある一方で、チケットのデータが蓄積されず、施策を打ちづらいというデメリットを感じていました。そのため、チケットの販売経路を公式プレイガイドのBチケ(Bリーグチケット)に一本化し、貯まったデータをベースにファンへのDM送付ができるようにするなど、序盤は基盤整備に重点を置きました。
――「ファンづくり」に焦点を当てたのはなぜですか。
主に2つの理由があります。最初は来場者数をKPIに設定し、効率の良い増加方法を調査・分析しました。その結果、友人・知人ら周囲から誘われて一緒に見に行った人のほうがファンとしての定着率が良く、継続して観戦していただける傾向にあるとわかりました。つまり、新規顧客を獲得して来場者数を拡大するためには、ファンを起点に施策を打つことが重要だと実感したのが1つめの理由です。
もう1つはアリーナのキャパシティの問題です。将来的には川崎市内に新しいアリーナの建設を考えているのですが、現状は約5000人が最大収容人数で、プロ野球やサッカーのスタジアムに比べると、規模は限定されています。そうするとチケットの売り上げだけでなく、アリーナ内に設置された看板の価値も自ずと制限され、スポンサー収入も観客動員数と同様、頭打ちになってしまいます。そこに追い打ちをかけるようにコロナがあり、50%の入場制限もかけられてしまいました。
そこで、アリーナを基準に思考するのではなく、別の活路を見いだす必要があると考え、来場者数にとらわれず、「ファン数」を新たなKPIに設定して、もっと広い見方をしようと決めました。
――具体的にはどんな見方ですか。
例えば、多くのファンがブレイブサンダースのYouTubeチャンネルに登録していただくと、チャンネル登録者数が積み上がります。その数字を評価してスポンサー企業が協賛してくださったり、大手企業との提携が生まれたり、提携がメディアに取り上げられて話題になったり、メディアを見て新しい人が来場してくださったりと、間接的な形で売り上げを作り、さらに新しい取り組みにつながります。ファンづくりにはそんな好循環を生み出して、ビジネスを拡大させる無限の可能性があると実感したのが2つめの理由です。

ブレイブサンダースが大きく数値を伸ばした理由
――YouTubeのチャンネル登録者数はBリーグだけでなく、サッカーのJリーグを含めてもブレイブサンダースが1位。TikTokのフォロワー数はプロ野球・読売ジャイアンツに次ぐ国内プロスポーツクラブ2位と、素晴らしいですね。デジタルマーケティングに取り組んでいるスポーツチームがいっぱいある中で、なぜブレイブサンダースは、こんなにすごい成果を出せたのでしょうか。
|
この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン