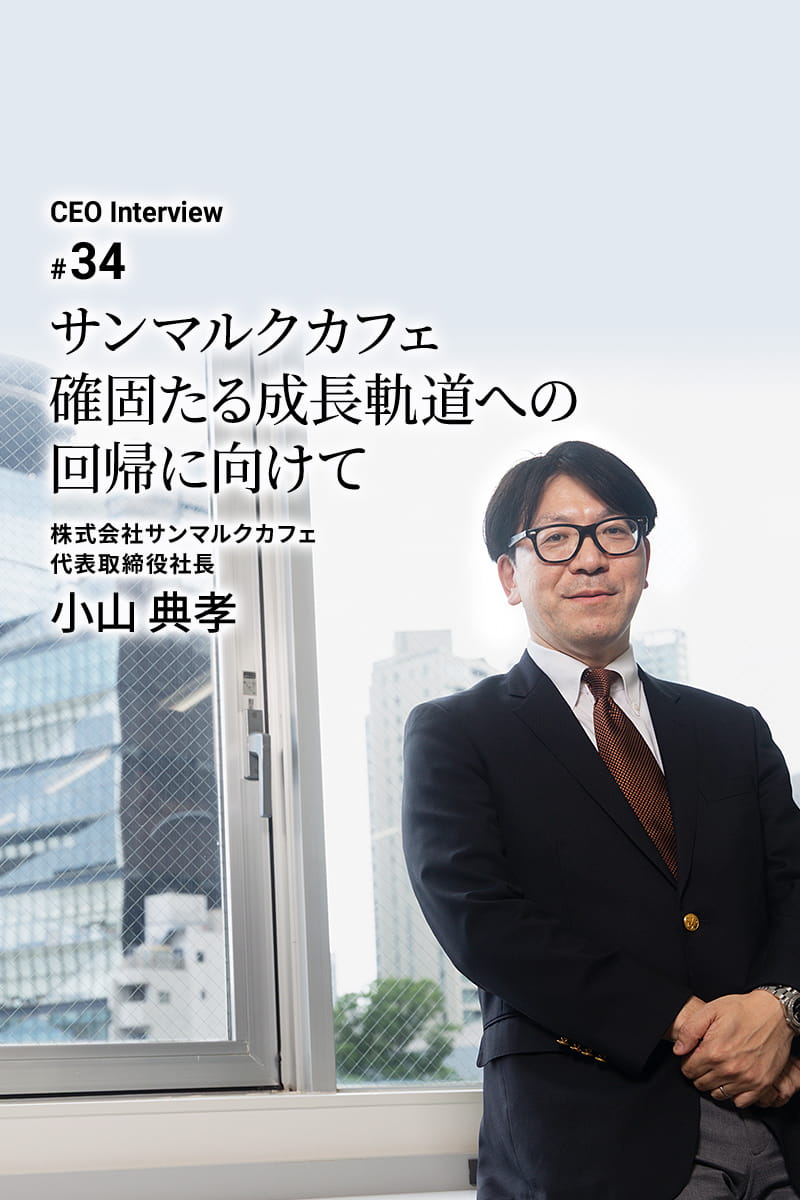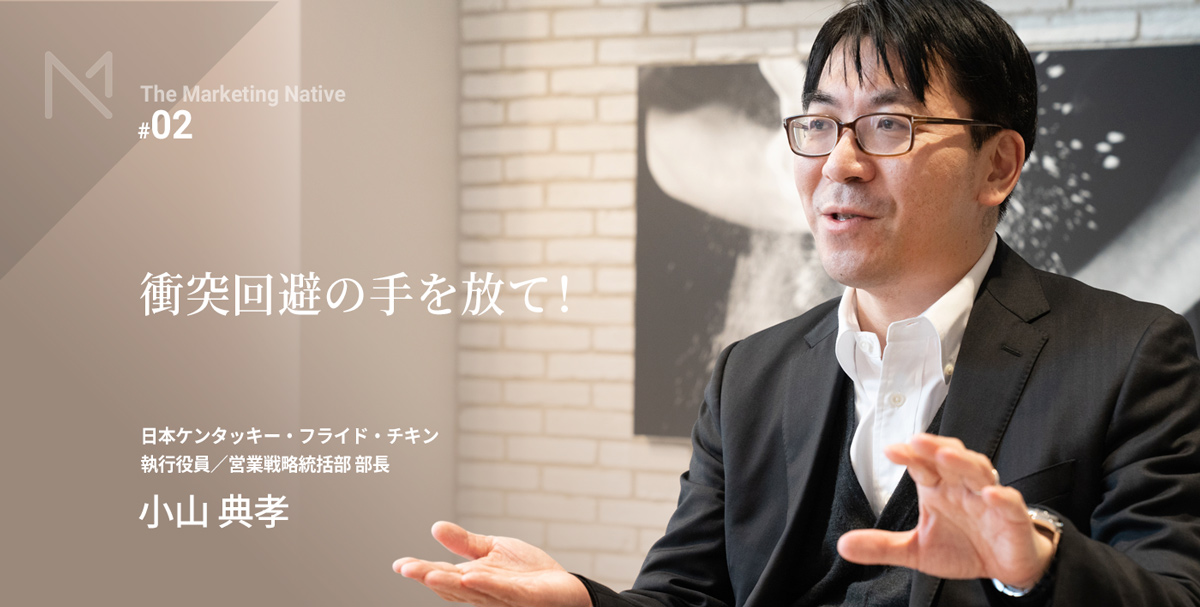コロナ禍で苦戦が伝えられたサンマルクカフェが、再成長に向けた新たな一歩を踏み出しました。その舵取りを担うのが、日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)で長年にわたり店舗開発やマーケティングを担当した後、今年(2025年)4月にサンマルクカフェの社長に就任した小山典孝さんです。
サンマルクカフェは一時、全国で400店舗近くありましたが、不採算店の整理などを経て、現在では300店舗を下回るまでに店舗数を減らしています。KFCで店舗数を増加させた実績を持つ小山さんは、これからどう立て直して再成長へ導こうとしているのでしょうか。
今回はサンマルクカフェ 代表取締役社長 小山典孝さんに話を聞きました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)
目次
キャリアの節目に芽生えた想い
――高校時代のアルバイトからKFC一筋だった小山さんが、サンマルクカフェの社長に就任されたと知り、驚きました。大きな決断だったと思います。移籍を決断したきっかけを教えてください。
私は今年55歳になりますが、KFCが日本に上陸したのも、私が生まれた1970年でした。KFCに入社したのは、そうしたご縁を感じたことも背景にあります。

昨年、KFCの株式がグローバル投資会社のカーライルさんに譲渡されました。株主が変わったことで方針や考え方の違いによる衝突が生じたわけではありませんが、ちょうど節目のタイミングでもあり、次の5年、10年をどう過ごすかを考えるようになりました。周囲の方々と話す中で、「5年後には60歳、10年後には65歳になる。ある意味キャリアの締めくくりに入っている今、何か新しいチャレンジをしたい」という前向きな気持ちが芽生え、今回の決断に至りました。
ですので、株主の変更はきっかけの1つではありましたが、対立や問題があったわけではなく、新たな一歩を踏み出したのは自らの意思です。
――サンマルクカフェを選んだ理由を教えてください。
もともと転職に関するさまざまな可能性を探る中で、方向性としては前職と同様に「食」に関わる仕事を続けたいと考えていました。その際、せっかく新たな環境に身を置くのであれば、前職ではアメリカ発のブランドを日本で展開していたため、今回はブランドを「借りる側」ではなく「貸す側」を経験したいと思いました。
また、サンマルクカフェに共通点を2つ感じたことも、決め手になりました。1つは、サンマルクホールディングスは岡山発の日本企業でありながら、店舗の雰囲気や取り扱う商材にどこか外国のアイデンティティを感じること。もう1つは、店舗で手作りをしているという点です。商材としてはチキンとチョコクロなどのパン類で異なりますが、「店舗で手作りする」というこだわりに共通点を感じ、好印象を抱きました。
――以前から転職先を探していたのですか。
前職では役員職が1年ごとの契約更新だったため、自分の意思にかかわらず「次は更新しない」と言われる可能性もゼロではありません。そのため、役員という立場の人は、多くの場合、常に転職市場における自身の価値を意識していると思います。
私自身も「良いお話があれば」と考えていましたが、株主の交代や55歳という年齢を機に、60歳という将来を現実的なものとして感じるようになりました。ちょうどそのタイミングで、「サンマルクカフェのリーダーを探している」というお話を頂戴し、自分の思いと相手のニーズが一致した、というのが実際のところです。
――もともとサンマルクカフェには好印象をお持ちだったのですね。
そうですね。サンマルクカフェの原点である「ベーカリーレストラン・サンマルク」は、パン食べ放題のレストランとして知られ、私も20代の頃に時折足を運んでいました。ファミリーレストランより少し特別感があり、ホテルよりはリーズナブルという印象です。
一部の店舗では、食事中にピアノの生演奏が行われることもあり、お祝い事にぴったりなおもてなしのあるブランドというイメージを持っていました。その印象は今も変わらず、自分の中で自然と「ご縁がある」と感じていたところがあります。

サンマルクカフェ再成長への展望と壁
――「社長」という立場はいかがですか。今回が初めての経験ですよね。
私は、マーケティングとは「商い全て」だと考えています。また、名経営者の中にはマーケター的な視点が優れている方が少なくないと感じます。私自身も、マーケティング活動の効率化と成果最大化を目的に、戦略の実行を支援する「オペレーションマーケター」を自認しており、その考え方は以前から変わりません。
ですから、社長というポジションになったからといって、マーケターとは全く異なる分野に進んだという意識はなく、見える景色が変わっただけだと思っています。もちろん責任はこれまで以上に重くなりますが、それも含めて新たなチャレンジとして前向きに捉えています。加えて、自分自身でロードマップを描くことができ、やりたいことがあれば主体的に取り組めることが多いため、大きなやりがいを感じます。
一方、ビジネスの現状を見ると、コロナ前は400店舗近くありましたが、コロナ禍の影響で300店舗を下回るまでに減少しました。ただし、不採算店舗の閉鎖による効率化は一段落し、「第二創業期」として成長軌道の入り口まで前任者の社長が整えてくださいました。今後はフランチャイズの導入を含め、次の展開へと進化させていく方針です。
このような拡大施策には、KFCで店舗開発を担当していた私の経験が十分に活かせると感じます。300〜400店舗規模と、1,000店舗を超える規模とでは、見える景色や課題も異なります。多業種・多角経営ではなく、単一ブランドで1,000店舗規模を展開していた経験は、サンマルクカフェのプロパー(生え抜き)社員の方々の中には少ないと思うので、私の知見を共有できればと考えています。
その意味では、社長としての責任の重さや不安よりも、むしろ楽しみのほうが大きいですね。

|
この記事は会員限定です。無料の会員に登録すると、続きをお読みいただけます。 ・利益体質への転換で成長基盤を強固に |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン