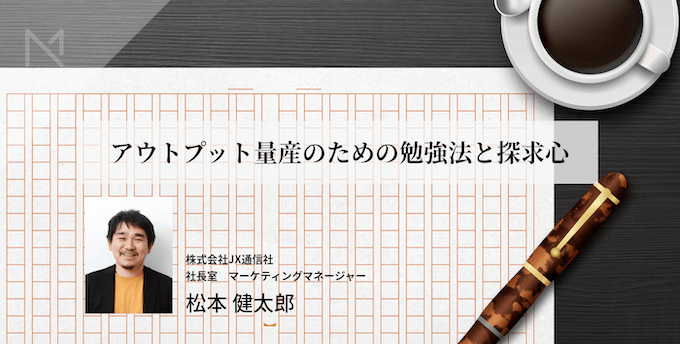データの分析を基に政治・経済・文化など世の中の事象に鋭く切り込む、データサイエンティストの松本健太郎さん。松本さんは現在、消費者の隠れた心理をインサイトリサーチで解き明かす株式会社デコムでR&D部門のマネージャーを務めています。
「低欲望社会」「現状満足時代」などと称される成熟した日本では、消費者はもはや大きな不満もなければ、欲しい物を聞かれても「別に…」と答えるだけでしょう。その一方で、いつの時代であっても大ヒット商品が誕生しないことはありません。本当は欲しい物はあるのです。
そのギャップを埋め、「特に欲しい物はない」と言う消費者に、「あなたが欲しい物はこれでしょう!」と提示する商品・サービスの開発に役立つのが「インサイト」です。
では、インサイトをどのように見つけ、それをアイデアとして具現化するにはどうすれば良いのでしょうか。
今回は株式会社デコムの松本健太郎さんをインタビューしました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、人物撮影:海保 竜平)
※肩書、内容などは記事公開時点のものです。
目次
データ万能主義への違和感から始まった消費者理解への道
――Twitterでは「松本さんのような記事を書きたい」「松本さんのようになりたい」との投稿も見られますので、まず経歴を教えてください。
わかりました。2007年に社会人としてスタートしまして、前職では主にデジタルマーケティングの効果測定を行う「アドエビス」の開発を行うエンジニアをしていました。プログラマーから始まり、プロジェクトリーダー、プロジェクトマネジメントなど「PMO」と呼ばれるプロジェクト管理でキャリアの大半を過ごしています。
その過程で、アドエビスで取得した膨大なデータを活用するプロジェクトに参加することになり、それがきっかけでデータサイエンスに興味を持ちました。

――エンジニアからデータサイエンティストに転身されたんですね。
はい、とはいえデータサイエンスを独学で身に付けるのはやはり難しく、私も苦戦しました。このままでは自分の成長に限界があると感じ、社会人大学院に2年間通ってデータサイエンスを学びました。
――松本さんは読書家だし、勉強家ですよね。
読書も勉強も好きだから続けているのですが、それ以上に毎日必死で勉強しないと取り残されるという危機感を強く持っているからだと思います。
ところが、私自身の才能の問題もあって、データサイエンスにのめり込んでいるうちに「データでわかることには限界がある」という結論に私自身の中で行き着いてしまいました。理由は、データサイエンスとは何かというと、世の中の森羅万象を数字に置換した上で分析して意思決定をすることなので、そもそも数字にできない領域をどう考えれば良いのかと疑問を持ったからです。また、仮に全てを数字にできたとしても、数字だけで世の中の全てを解釈するのは無理があると思いました。
キャリアの中でこんな経験をしました。あるブランドワードの流入が直帰率60%で、Webサイト全体の直帰率80~90%と比較して優秀な数字だと考えていたら、ブランドの責任者に怒られたんです。「お客さまが自社の商品名でWebサイトを訪問しているということは、購入する気満々か、何か情報を知りたいかのどちらかなので、直帰率は0%でなければおかしい」と言うんですね。責任者が言いたいことはわかります。そんなことは現実にはないわけですが、「直帰率60%の理由は何ですか?」「なぜ答えられないんですか?」と聞かれて十分な回答を提示できない現実に直面したとき、「自分の考えているデータマーケティングの世界は、ブランド観点で見ると非常識なのかもしれない」「データがあれば全てわかるという考え方はおこがましいのではないか」と感じるようになりました。そこから消費者理解に興味を持ち始め、大学院時代に知り合った大松(孝弘さん)が代表取締役を務めるデコムに転籍しました。

「CVが20倍になるように考えてくれ」
|
この記事は会員限定です。登録すると、続きをお読みいただけます。 ・インサイト発見につながる、観点ずらしの発想法 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン