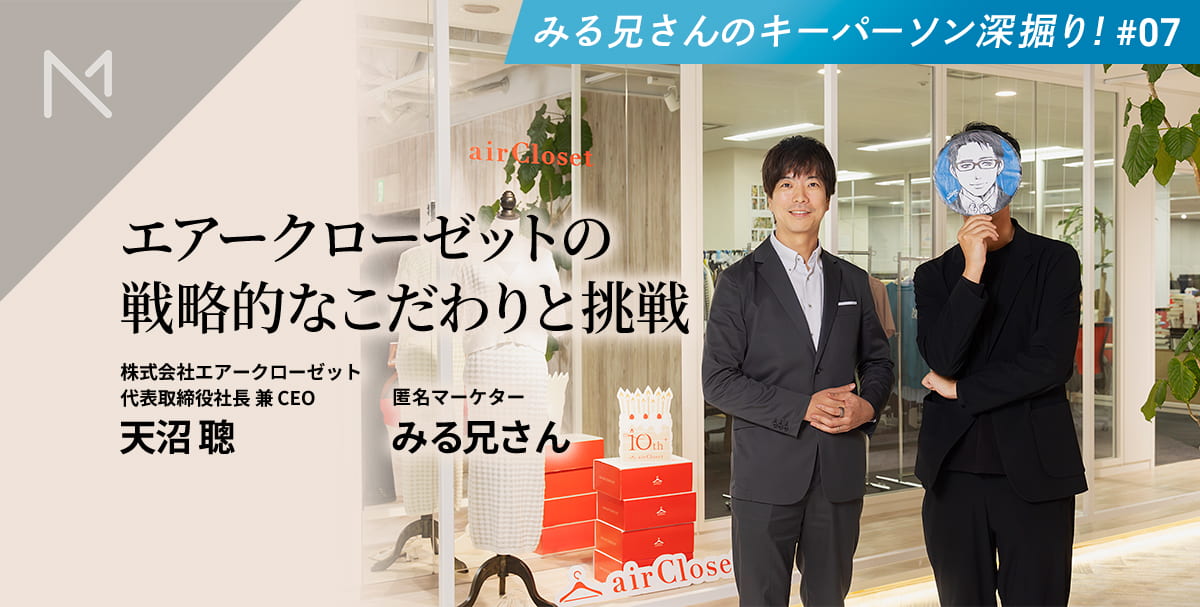創業90年余、家庭用ジャムで国内トップの約30%のシェアを持つアヲハタ。人気の背景には、こだわりの原料調達力と素材の味を最大限に活かす加工技術があります。
そのアヲハタでマーケティングと研究開発をリードするのが、同社で女性初の取締役を務める藤原かおりさんです。藤原さんは、ジャムブランドの強化とともに、新商品の投入で新たな市場を開拓し、ジャムの枠を超えたブランドの拡大に取り組んでいます。
どんな戦略を描いているのでしょうか。今回はアヲハタ取締役の藤原かおりさんに話を聞きました。
(取材・構成:Marketing Native編集部・早川 巧、文:和泉 ゆかり、撮影・永山 昌克)
目次
前職で「フルグラ」の売り上げを5年で10倍に
――藤原さんは新卒で旭硝子に入り、マッキャンエリクソン、電通、ダノンウォーターズオブジャパンを経て、カルビーへ。同社で「フルグラ」の成功をリードし、2017年には執行役員に就任。その後、2020年3月にキユーピーへ転職し、女性初・最年少の上席執行役員に就任され、2024年2月からアヲハタで女性初の取締役としてご活躍されています。
過去のインタビューでは「旭硝子で鍛えていただいてから、ずっとマーケティングを愛しています」と発言されていますね。
旭硝子での経験が、マーケティングの道で生きていこうと決めた原点になっています。当時はエレクトロニクス部門で新規事業開発に携わり、調査やインタビューを重ねて市場分析をしながら、どこにビジネスチャンスがあるかを掘り起こしていくプロセスを大変興味深く感じていました。また、優秀な先輩方と働けたことも興味関心を深める要因だったと思います。
その後、ダノンに入ってから「食の分野をもっと極めたい」と思うようになりました。

私の経験上、日本の食品会社では一般的に、商品開発がマーケティング業務の中心に位置づけられ、広告宣伝部が別部署として存在する傾向があると感じます。一方、ダノンのような外資系企業では、ブランドマネージャーがマーケティングの中核を担っており、4P(Product、Place、Price、Promotion)すべてを統合的にマネジメントしています。外資は専門性を高める研修も整備されていて、私もダノンという外資系企業で働くことで、食のマーケティングに関する専門性を身につけることができました。その結果として、「食の分野をもっと極めたい」と思うようになったのです。
――藤原さんにとって、これまでの最大の実績は、カルビー時代にフルグラを5年間で売り上げ30億円から300億円に伸ばす成功を収めたことでしょうか。どのような戦略だったのか、マーケティングの観点を中心に教えてください。
最初に取り組んだのは「売り上げを100億円まで拡大する」という目標の達成でした。まず行ったのが、ターゲットの明確化です。働く女性にターゲットを絞り、「忙しい女性の朝食」として商品を根づかせることを目指してマーケティングを展開しました。特に子育て中の方は朝、とても忙しいと思います。
加えて行ったのが、従来とは異なる食べ方の提案です。当時「シリアルは牛乳をかけて食べるもの」という認識が一般的でしたが、食卓の実態を分析してみると、大人になると牛乳を飲む機会は減る一方で、ヨーグルトは多くの方がよく食べていることがわかりました。そこで、シリアルをヨーグルトと一緒に食べることを提案しました。
このようにターゲットを絞り、ニーズに合わせたマーケティングを行ったことが成功につながったと考えています。
――ターゲットを絞らずに老若男女すべての人たちに購入してもらうほうが良いのではないかと考えがちですが、やはりターゲットを絞り込むほうが効果的でしょうか。
最初はターゲットを絞り込み、十分に浸透したと判断できれば、次は別の層を狙うというように順を追って展開していくのが基本です。最初から幅広く訴求してしまうと、何を目的としている商品なのか世の中に伝わりにくくなってしまいます。
――主にターゲットを絞ったりヨーグルトとの食べ方を提案したりしたことが奏功し、売り上げ100億円を達成したとのことですが、その後300億円まで拡大するために、どのようなことに取り組みましたか。
200億円くらいまでは、ターゲット層の方々にしっかりと商品を認知・購入してもらうべく、働く女性がよく目にするであろう媒体を中心に、多くのメディアに取り上げられるようPRを戦略的に展開しました。また、狙っていたわけではありませんが、インバウンド需要が大幅に拡大したことが、300億円達成の要因のひとつになりました。

「ジャムといえば…」ではなく、「フルーツといえばアヲハタ」に
――アヲハタの取締役に就任して約1年5カ月(2025年7月の記事公開時点)。この間に見えてきたアヲハタの強みを教えてください。
まず挙げられるのが、原料調達力です。多くのメーカーでは、サプライヤーが持参したカタログの中から商品を選定するケースが一般的ですが、アヲハタでは基本的に、自分たちで実際に国内外を問わず、足を運んで選定しています。国・畑・品種、それぞれ何が最適か、その商品にベストな原料を的確に選んで調達できるのは、長年自分の目で確かめて選定してきた経験があるからです。
また、加工技術にも自信があります。アヲハタはフルーツ缶詰から事業をスタートした会社です。そのため、フルーツ加工技術に関しては技術の幅が広く、さらに調理食品も手掛けているので、豊富なノウハウが蓄積されています。
このように多様な技術とノウハウが蓄積されているため、新商品に関する要望を出すと、期待以上のものがすぐに開発されてきます。マーケターとしてはとても恵まれている環境です。
――冷凍フルーツ事業が伸びていると伺いました。
ありがとうございます。認知度を正確に調査できていませんが、実際はまだまだ知られていないのが現状だと思います。店舗での配荷もこれから本格的に進めていきます。2店舗あったら1店舗には必ず置いてあるくらいの状態に広げていきたいです。
目指すのは「ジャムといえばアヲハタ」を超えて、「フルーツといえばアヲハタ」と皆さまに思っていただくことです。現状はまだジャムを連想される方が多いため、ジャム以外の商品ももっと展開して、パーセプションを変えていくことに力を入れていきます。
――アヲハタのマーケティングの特徴について教えてください。現状については「ジャムといえばアヲハタ」という認知があり、特に強い競合もほとんど見当たらない中で、認知度やシェアの争いをそれほど意識しなくて良い状況だと思いますが、どのようなマーケティングを展開しているのでしょうか。
|
この記事は会員限定です。無料の会員に登録すると、続きをお読みいただけます。 ・ジャム以外も好調、パン関連商品全体で事業拡大 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン