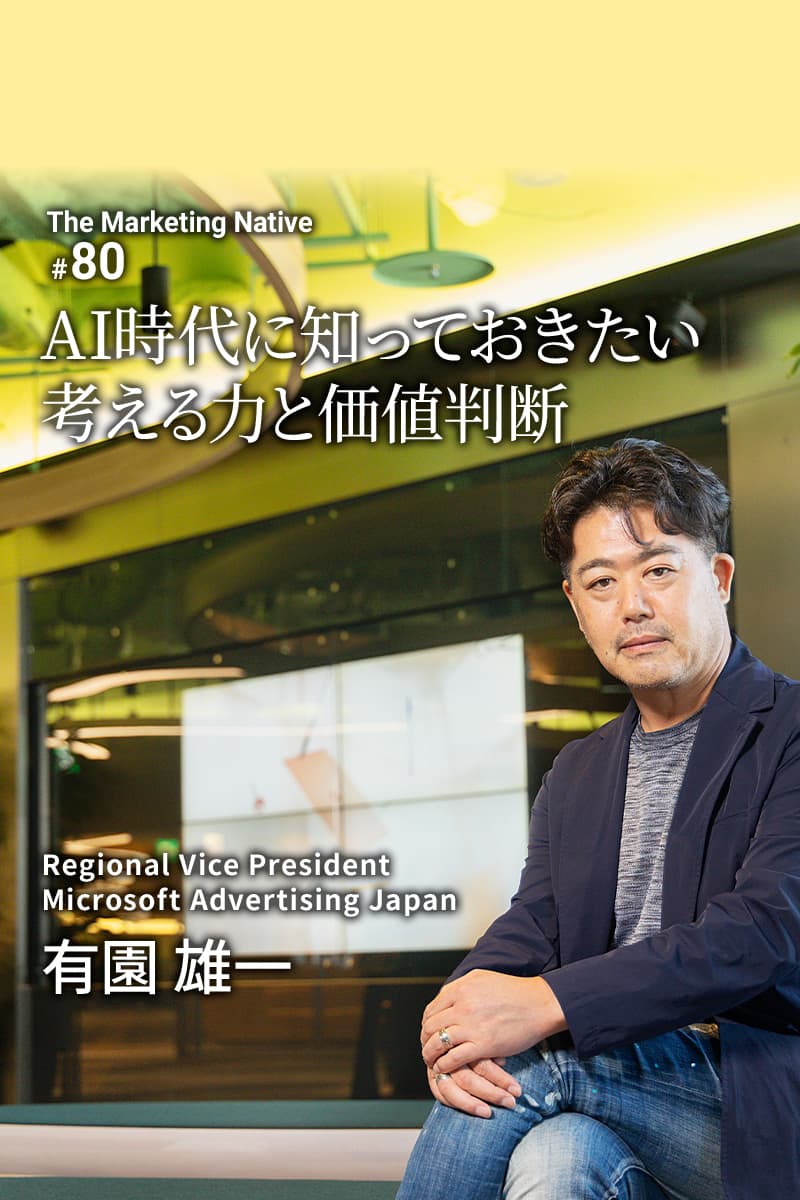生成AIが台頭し、アイデアの発想から広告運用、レポート作成に至るまで、マーケティングの領域はかつてないスピードで変化が見られます。
そんな中、「AIの進化で、考える力が退化するのでは」「マーケティングはAIにほぼ代替される」など不安の声も聞かれます。
AI時代に求められる「考える力」とはどんなことでしょうか。今回はMicrosoft Advertising Japan, Regional Vice Presidentの有園雄一さんをインタビュー。事故で生死をさまよった経験から、考え続けることを自らの習慣としてきた有園さんに、マーケターが「考えるプロ」として生きるために必要な視点を伺いました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)
目次
病院のベッドで始まった「考えるしかない」日々の葛藤
――「AI時代の考える力」についてお伺いする前に、有園さんご自身は、これまでどのように「考える力」を培ってこられたのか教えてください。
まずは、少し真面目な話から始めさせてください。個人的なことになりますが、私は高校を卒業して間もない19歳のとき、タンクローリーに轢かれるという交通事故に遭いました。奇跡的に命は助かりましたが、幽体離脱のような体験もし、本当に死んでいてもおかしくない状況だったと思います。
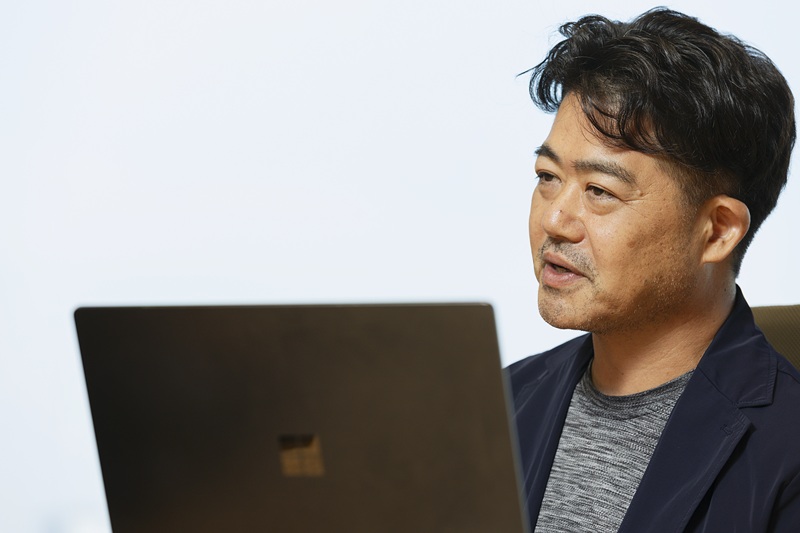
その後しばらく入院生活を送りましたが、病院のベッドでできることといえば、考えることくらいしかありません。そのとき、よく頭に浮かんできたのは、「たとえ自分がこの事故で死んでいたとしても、世の中は何も変わらないのではないか」という考えでした。
それは私ひとりのことだけではありません。当時、イギリスではサッチャー首相、アメリカではレーガン大統領、そしてソ連(現ロシア)ではゴルバチョフ書記長がそれぞれ国のトップを務めていました。しかし、仮にその人たちが亡くなったとしても、世の中が大きく変わることはないだろう――そんなふうに思ったのです。
では、自分が生きていること、生きている価値とは一体何だろうか。実際は自分が生きていても死んでいても、それほど大きな違いはないのではないか――そう思いながら、なぜ自分は生き続けなければならないのかを考えてきました。「考える力が重要」という以前に、病院のベッドの上では、考えて、考えて、考え抜くことしかできなかったのです。
自分の生きる意味は何か。人類はなぜ存在しているのか。宇宙はどのように誕生し、何のために存在しているのか――そうした問いを考え抜き、自分の中で折り合いをつけなければ、生きていることが苦しくて仕方がなかった、そんな感覚でした。
――今は大丈夫ですか。
その後も、その感覚は自分の中の底辺にずっと存在しています。だからこそ、一つひとつの物事の意味を考えざるを得ないのです。なぜ生きるのか。なぜ食べるのか。なぜ排泄するのか。
仕事についても、自分なりに意味を考え、納得した上でインターネット広告という事業に向き合っています。普通の人よりは読書量も多いと思いますし、AIが人類にどのようなインパクトを与えるのかという点も含め、今もひたすら考え続けています。
したがって、「考える力をどのように培ってきたのか」という問いに対しての答えはこうです。「私は九死に一生を得る事故を経験したことで、一つひとつのことを考えずにはいられない人間になり、そのまま今も“考える”という癖が身についている」と。

人間だけにできる「考える」行為と、「真・善・美」の価値判断
――次に、AIが進化していく中で、人間が考える意味は、どのような形で残っていくとお考えですか。
|
この記事は会員限定です。無料の会員に登録すると、続きをお読みいただけます。 ・AIが強い内生変数と、人間が担う非デジタルな外生変数 |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン