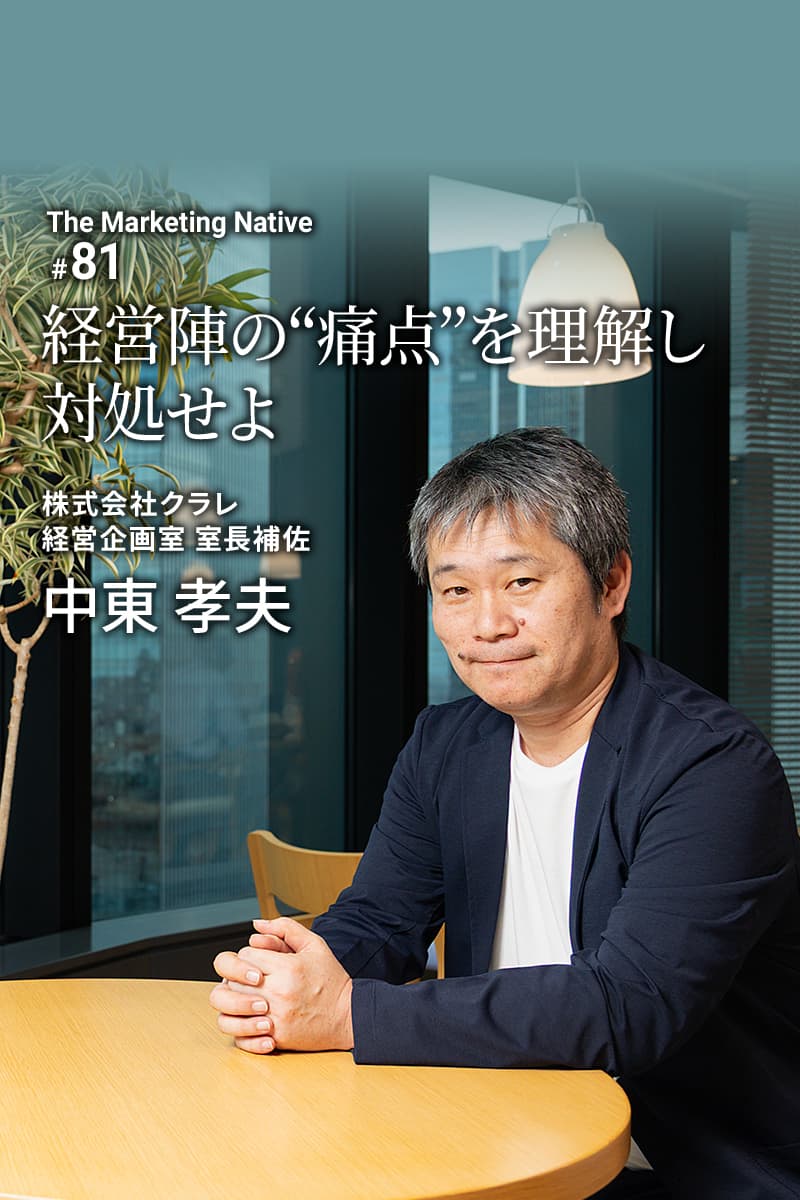生成AIの進化によって、マーケティングの実務は急速に自動化が進んでいます。一方で、30〜40代の中堅マーケターからは「この先、どんな形で価値を発揮すればいいのか」と悩む声も聞かれます。
今回は、クラレ 経営企画室 室長補佐の中東孝夫さんをインタビュー。中堅層のBtoBマーケターが考えたいAIとの向き合い方をはじめ、キャリアの活かし方や価値の出し方、そして仕事に「飽き」を感じたときの対処法などを伺いました。
(取材・文:Marketing Native編集部・早川 巧、撮影:矢島 宏樹)
目次
これからのマーケターに求められる能力
――マーケターの方々を取材していると、30代、40代の中には「これから自分はどうすればよいのか」と悩んでいる人に出会うことがあります。「マーケターとしては、ある程度やり尽くした気がする」「生成AIがマーケティング業務を代替するようになると、居場所がなくなるのではないか」といった声も聞かれます。そこで今回は、これからのマーケターの生き方について、中東さんがどのようにお考えなのかを伺いたいと思います。
その前にまずキャリアについてお聞かせください。現在はクラレの経営企画室で室長補佐を務めていらっしゃるとのこと。具体的にどのような業務を担当されていますか。
経営企画室の中では、主にマーケティング領域において「今、対応すべき課題を自ら見つけ、主体的に仕事をつくる」ことをミッションとしています。そのため、私の担当するマーケティングとは、広告やWebマーケティングなどの施策の話ではなく、グローバル企業としてのクラレのガバナンス/コンプライアンス、人的資本形成などの基盤を整理し、経営陣に提案する役割です。

――プロフィルを拝見すると、消費財メーカーから外資系IT企業、大手通信会社、スタートアップと、多彩なキャリアを積まれています。社会人としての経験は約30年とのことですが、ずっとBtoB領域に携わってきたのでしょうか。
「エリエール」で知られる大王製紙でBtoCのブランドマネジメントを経験し、その後「Lotus 1-2-3」で知られるロータスへ転職。そこでBtoBマーケティングの面白さに引き込まれました。以降はKDDIの部長時代を含め、25年以上、BtoBマーケティングに携わっています。
――AIについてお聞きします。近年、マーケティング業務においても生成AIの活用が欠かせなくなってきました。AIの導入で中東さんの仕事の進め方に変化はありましたか。
大いに変化しました。最近はGTM(Go-to-Market)戦略の全体像をAIに作成させています。業界団体であるデジタルマーケティング研究機構にて、各国独自に展開されていたモデルを整理・統合してBtoBに向けて標準化し、その成果をGTM標準プランニングモデルとして取りまとめ、発表しました。
現在はそのモデルをもとに、AIが市場規模やバリューチェーンを分析し、戦略提案まで自動生成できるようになっています。
――すごいですね。やはり生成AIがあれば、マーケティング業務の多くが代替され、マーケターは不要になってしまうのではないかと感じてしまいます。こうした時代において、マーケターはどのように価値を発揮すべきとお考えですか。
「問いに答える作業」は大きく効率化されると思います。しかしマーケティングに限らず、「問いを立てる力」は、今のところAIには存在しません。ここが重要なポイントになります。これからのマーケターに最も求められる能力のひとつは、「問いを立てる力」だと思います。
価値のある答えを引き出すためには、良い問いが必要です。ただし、GTMのプロンプト作成でも同様で、「アカウントとバイイングセンターを定義し、バリュープロポジションを明確にして」などと、良い問いを立てるためには専門的な観点から精緻に問いを立てられる知識が求められます。専門的な知識がなければ、AIに対して「いい感じの戦略を立てて」などと曖昧な指示しかできず、望むような答えは返ってきません。逆に、問いを精度高く設計できれば、AIからは的確な答えが返ってきます。
一般的にも、「面白そうな企画を出して」では、成果を出すのは難しいでしょう。しかし、あらかじめ領域やテーマ、切り口を指示されれば、アウトプットしやすくなります。AIも同様です。
一度「良い問い」(プロンプト)が構築されれば、あとは多くの作業をAIが自動化できます。例えばデータリサーチや課題抽出、課題解決策の提案、実行計画の立案、さらにコピーワーク、バナー案の提示、LPのコーディングなどは、ほとんどAIで対応可能です。したがって、将来的には答えに関する作業部分では人手をあまり必要としなくなるかもしれません。

時代の変化の中で、中堅以上のマーケターが求められること
――問いを立てるだけであれば、マーケターの数はそんなに多くは要らないですよね。
確かに、初期の問いの設計には専門性が要りますが、一度それが完成すれば、他の人もその枠組みを使って成果を出せます。つまり、専門知識を持つ人が「問いのテンプレート」をつくり、それを活用できる人が増えていくという構造です。その昔、パソコンが普及したらオフィスワーカーは減る、という話がありましたが、そんなことにはなっていないのと同じですね。
AIの浸透の結果、これまでバナー入稿などの実務に追われていた人たちも、その意欲によって、より上流の仕事に携われるようになります。GTM 戦略の標準モデルも、AIに適切なプロンプトを渡し、製品名などを差し替えるだけで、一定の品質を保った成果物を生成できるようになっています。そうなれば、新入社員であってもGTM戦略の議論に参加できるようになり、むしろマーケター活躍の場は広がっていくと考えています。
――しかし、それでは新入社員も、30代・40代のマーケターも、あまり差がなくなってしまいますね。
|
この記事は会員限定です。無料の会員に登録すると、続きをお読みいただけます。 ・「さすがベテラン」と信頼されるスキルとは |
 会員登録
会員登録 ログイン
ログイン